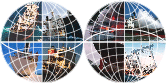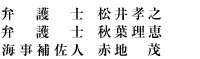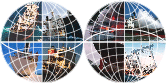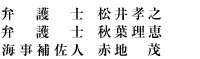����22�N7��27���������n�@�������{�̎��@�ٔ������L��
����17�N�i���j��21650�����Q�������������i�ȉ��u��1�����v�Ƃ����B�j
����17�N�i���j��21651�����������������i�ȉ��u��2�����v�Ƃ����B�j
����17�N�i���j��21758�����Q�������������i�ȉ��u��3�����v�Ƃ����B�j
����19�N�i���j��27594�����Q�������������i�ȉ��u��4�����v�Ƃ����B�j
����20�N�i���j��2778�����Q�������������i�ȉ��u��5�����v�Ƃ����B�j
�����٘_�I�����@����21�N12��22��
���@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�����҂̕\���@�ʎ��u�����ژ^�v�A�u�����㗝�l�ژ^�v�y�сu�퍐���ژ^�v�ɋL�ڂ̂Ƃ���
��@�@�@�@�@�@�@�@�@��
1 ������̐���������������p����B
2 �i�ה�p�i�⏕�Q���ɂ���Đ�������p���܂ށB�j
�͌�����̕��S�Ƃ���B
���@���@�y�@�с@���@�R
��1�@����
�ʎ��u�����ژ^�v�ɋL�ڂ̂Ƃ���
��2�@���Ă̊T�v
1�@�n���C����q�s���̃R���e�i�D�̑D�q���ɂ����č��M�̔����y�є��������́i�ȉ��u�{�����́v�Ƃ����B�j���������A�X�ɂ���ɑΉ����邽�ߑD�q���ւ̎U���A�����A�C���̒������̑[�u���Ƃ�ꂽ���ʁA�R���e�i�D�̑D�̂�ωׂɔj���␅�G��Ƃ��������Q�����������B�{���́A�R���e�i�D�̗��b�D�ҁA�ݕ��̉ב��l���͉�l�Ƃ̊Ԃʼnݕ��C��ی��_���������Ă������Q�ی���Ђł��錴���炪�A�퍐���ב��l�ƂȂ��Ă����ݕ����댯���ł������ɂ�������炸�A�퍐���댯���̉ב����Ƃ��ċ`���t�����Ă����ݕ����댯���ł���|�̕\���`�����̒��Ӌ`����ӂ������ʁA���ݕ����ύڂ��ꂽ�R���e�i���D�q���̔M���ɋ߂��ꏊ�ɐςݕt�����A���M�������N�����Ė{�����̂Ɏ������Ƃ��āA�퍐�ɑ��A�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����������i�ی���ʖ��͍����n�ɂ���Ď擾�������̂��܂ށB�j�Ɋ�Â��āA���Q�����i��ʓI�����͑��Q���O���ĂŁA�\���I�����͑��Q���~���Ăł��ꂼ��Z�肵�����́j�̎x�������߂��i�ׂł���B
2�@�O��ƂȂ鎖���i�؋������f�L�������̈ȊO�͓����ҊԂɑ������Ȃ��B�j
(1)�A�@�����G�k���C�P�[�E�A���O�X�E�R�[�|���[�V�����i�ȉ��u����NYK�v�Ƃ����B�j�́A���{�X�D������Ёi�ȉ��u���{�X�D�v�Ƃ����B�j�̊֘A��Ђł���B
�C�@�����O��Z�F�C��Еی�������Ёi�ȉ��u�����O��Z�F�C��v�Ƃ����B�j�A�����x�m�ЊC��ی�������Ёi�ȉ��u�����x�m�Ёv�Ƃ����B�j�A���������C������Еی�������Ёi�����̏����́A�����C��Еی�������ЁB���Ђ́A����16�N10��1���A�����ЊC��ی�������Ђƍ������ď����ύX�����B�ȉ��u���������C������v�Ƃ����B�j�A���������������Q�ی�������Ёi�ȉ��u���������������ہv�Ƃ����B�j�A����������Б��Q�ی��W���p���i�ȉ��u�������ۃW���p���v�Ƃ����B�j�A�����j�b�Z�C���a���Q�ی�������Ёi�ȉ��u�����j�c�Z�C���a�v�Ƃ����B�j�y�ь������{�������Q�ی�������Ёi�ȉ��u�������{�������ہv�Ƃ����B�j�́A��������ݕ��C��ی����܂ފe�푹�Q�ی��̈����ƂƂ��銔����Ђł���A�����\���|�E�W���p���E�C���V���A���\�X�E�J���p�j�[�E�I�u�E���[���b�p�E���~�e�b�h�i�ȉ��u�����\���|�E�W���p���E���[���b�p�v�Ƃ����B�j�A�����t�H�[�e�B�X�E�R�[�|���[�g�E�C���V���A�����X�E�G�k�E�u�C�i�ȉ��u�����t�H�[�e�B�X�v�Ƃ����B�j�A�����G�C�S���E�V���[�f�t�F���[�[�P�����O�E�G�k�E�u�C�i�ȉ��u�����G�C�S���v�Ƃ����B�j�A�����g�[�L���[�E�}�����E���[���b�p�E�C���V���A�����X�E���~�e�b�h�i�ȉ��u�����g�[�L���[�E�}�����E���[���b�p�v�Ƃ����B�j�A�����o�����[�E�C���V���A�����X�E�J���p�j�[�E���~�e�b�h�i�ȉ��u�����o�����[�v�Ƃ����B�j�A�����A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\�����[�V�����Y�E�j�[�_�[���b�T���N�E�h�C�b�`�F�����g�E�f�A�E�A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\�����[�V�����Y�E�A�V���A�����X�i�ȉ��u�����A�N�T�v�Ƃ����B�j�A�����}���n�C�}�[�E�t�F�A�Y�C�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�i�ȉ��u�����}���n�C�}�[�v�Ƃ����B�j�A�����N���o�O�[�A���Q�}�C�l�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�i�ȉ��u�����N���o�O�[�A���Q�}�C�l�v�Ƃ����B�j�A�����r�N�g���A�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�i�ȉ��u�����r�N�g���A�v�Ƃ����B�j�A�����G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O�E�C���h�D�X�g�D���[�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�i�ȉ��u�����G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O�v�Ƃ����B�j�A�����R���h�A�E�g�����X�|�[�g�[�A���h�E���b�N�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�i�ȉ��u�����R���h�A�v�Ƃ����B�j�y�ь������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�E�T�b�N�E�t�H���Z�[�N�����O�T�b�N�e�B�{���O�i�ȉ��u�������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�v�Ƃ����B�j�́A���Q�ی��Ɠ����ƂƂ���O����Ђł���B
�E�@�����[���b�N�X�E���~�e�b�h�i�ȉ��u�����[���b�N�X�v�Ƃ����B�j�́A�d���@��y�ъ֘A�����i�̐����A�̔������ƂƂ���O����Ђł���A�������}�U�L�E�}�U�b�N�E���[�P�[�E���~�e�b�h�i�ȉ��u�������}�U�L�v�Ƃ����B�j�́A�������@�B�̐��������ƂƂ���O����Ђł���B�H�퍐�́A����17�N3��24�������A���Ɠo�L���̖ړI�Ƃ��āA���w���i�y�т�����ޗ��Ƃ��鐻�i�A���i�y�ш�O�i���тɉ��w���i���̗A�o�A�A���y�є̔����f���Ă������Ђł���i�b�C6�j�B
�I�@�퍐�⏕�Q���l�_�C�g�[�P�~�b�N�X������Ёi�ȉ��u�⏕�Q���l�_�C�g�[�v�Ƃ����B�j�́A�uNA�[125�v�Ƃ������̂̏��i�i���w���u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���v�A���q���uC10H6N2O4S.Na.H2O�v�j�y�сuPSR�[80�v�Ƃ������̂̏��i�i���w���u�A�Z�g���ƃs���K���[���̏k������1�A2�[�i�t�g�L�m���[�i2�j�[�W�A�W�h�[5�[�X���z���_�G�X�e���v�A���q���uC10H6N2O4.���iC6H6O3.C3H6O�jx�j�B�v�j�̐����҂ł���i����13�A14�k�}�Ԃ��܂ށl�j�B
�i2�j �ʎ��u�{�D�̊T�v�v�L�ڂ̑D���G�k���C�P�[�E�A���O�X���i�ȉ��u�{�D�v�Ƃ����B�j�́A�p�{�E���C���E�V�b�s���O�E�G�X�E�G�C�����L����R���e�i�D�ł���B����16�N�����A���Ђ���O�����A�X�E���o�[�E���C���E�G�X�E�G�C���A���Ђ��猴��NYK���A����NYK������{�X�D���A�����{�D��b�D������A���{�X�D���{�D���A�W�A���B�Ԃ̒���q�H�ɔz�D���Ă����B
�i3�j �퍐�́A����16�N9���A�퍐�⏕�Q���l�p���e�i�[�E���~�e�b�h�i�ȉ��u�⏕�Q���l�p���e�i�[�v�Ƃ����B�j��㗝�����퍐�⏕�Q���l�p�i���s�i�E���[���h�E�g�����X�|�[�g�E�W���p��������Ёi�ȉ��u�⏕�Q���l�p�i���s�i�v�Ƃ����B�j�Ƃ̊ԂŁA�퍐���ב��l�A�⏕�Q���l�p���e�i�[���^���l�Ƃ��āA�⏕�Q���l�_�C�g�[����w���������̊e�ݕ��i�ȉ��u�{���e�ݕ��v�Ƃ����B�j��_�˂��烍�b�e���_���܂ʼn^������|�̌_�����������B
�A NA-125 50Kg����t�@�C�o�[�h������10O��
�C PSR�[80 10Kg����J�[�g��40��
�i4�j �⏕�Q���l�p���e�i�[��㗝�����⏕�Q���l�p�i���s�i�́A�f�C�[�E�G���E�R���\�ꃋ�E���C���i�ȉ��u�_���R�v�Ƃ����B�j�Ƃ̊ԂŁA�{���e�ݕ��̉^���_���������A�_���R�́A�X�Ƀs�[�E�A���h�E�I�[�E�l�h���C�h�Ёi�ȉ��u�s�[�E�A���h�E�I�[�v�Ƃ����B�j�Ƃ̊ԂŁA�{���e�ݕ��̉^���_�����������B�����āA�_���R�̑㗝�X���C�^������Ёi�ȉ��u���C�^�v�Ƃ����B�j�̉�����Ђł���쐼�q�Ɋ�����Ёi�ȉ��u�쐼�q�Ɂv�Ƃ����B�j�́A�s�[�E�A���h�E�I�[���L�̃R���e�i�i�R���e�i�ԍ�OCLU0949259�B�ȉ��u�{���R���e�i�v�Ƃ����B�j�ɑ��̉ݕ��ƂƂ��ɖ{���e�ݕ���ύڂ����i�ȉ��A����NYK�A�⏕�Q���l�p���e�i�[�A�⏕�Q���l�p�i���s�i�A�s�[�E�A���h�E�I�[�A���{�X�D���{�D�̉^�q�Ɋւ��҂̂��āu�{�D���v�Ƃ����B�j�B
�i5�j �{���e�ݕ��Ɋ댯���ł��邱�Ƃ������W�����͕t����Ă��炸�A�{�D���́A�{���e�ݕ����댯���̈�ʉݕ��Ƃ��Ĉ����A�{���R���e�i��ʎ��u�{�D�̊T�v�v�L��9�̂Ƃ���A�{�D�̑�3�D�q�̑�23���E��8��E��2�w�i23�E08�E02�j�ɐςݕt�������A�{���R���e�i�̉����y�э������́A��10�Ȃ���15cm�̋i��C�w�j���u�ĂĖ{�D�̍�����3�R�����^���N�ɖʂ����ԂƂȂ��Ă����i�b�C3�A�b�n8�j�B
�i6�j �{�D�́A����16�N9��28���A�_�˂��o�`���A���̌�A���É��A�����A�����Ɋ�`���A�X�ɃV���K�|�[���Ɋ�`������ŁA���N10��8���A�V���K�|�[������T�U���v�g���i�p���j�����ďo�`���A����17���ɂ́A�X�G�Y�^�͂�ʉ߂��Ēn���C���q�s���Ă����B�Ȃ��A�����ߌ�5������A�{���R���A�e�i�ɖʂ���{�D������3�R�����^���N�̔R�����ɂ��āA���̗��������m�ۂ��邽�߁A���M���J�n���ꂽ�B�{�D������19���ߌ�11��55�����i���n���ԁB�ȉ������B�j�A�k��38�x�A���o6�x39��3�b�t�߂��q�s���A��3�D�q�̉��T�m�@���x�����B�{�D�̑D����́A��3�D�q������̉��̔����y�т��̕t�߂̉��x�㏸���m�F�������Ƃ���A��3�D�q�𖧕�Ԃɂ��āA��3�D�q�ɓ�_���Y�f����o���A�܂��A�C���X�v�����N���[���쓮�����đ�3�D�q���ɊC�����U������Ȃǂ��āA����ɑΉ������Ƃ���i�ȉ��u�{�����������v�Ƃ����B�j�A����20���ߑO11������A�����F�߂��Ȃ��Ȃ�A���x���ቺ�������Ƃ��玖�Ԃ̒��Â��m�F�����B
�i7�j �{�D�́A����24���ɃT�U���v�g���Ɋ�`���A����28���Ƀ��b�e���_���ɓ��������B���̍ہA�ωׂ̉חg�����s����ƂƂ��ɁA����29���ߌ�3���ɑ�3�D�q�̃n�b�`���J������Ė{�����̂̔��������̒������s��ꂽ�i�b�n9�j�B
3�@���_
�i1�j�{���e�ݕ��̊댯���Y�����i���_1�j
�i2�j�{�����̂̌����i���_2�j
�i3�j���̐ӔC�Ɋւ���@���i����32�N�@����40���B�ȉ��u���ΐӔC�@�v�Ƃ����B�j�̓K�p�̗L���i���_3�j
�i4�j�퍐�̉ߎ����͏d�ߎ��̗L���i���_4�j
�i5�j���Q�̗L���y�ъz�i���_5�j
�i6�j���v���E�|�����C�����S���������̗L���i���_6�j
�i7�j���Ŏ����̐���1�i���_7�j
�i8�j���Ŏ����̐���2�i���_8�j
4�@���_�ɑ��铖���҂̎咣
�i1�j���_1�i�{���e�ݕ��̊댯���Y�����j
�i������̎咣�j
�A �{�����̔��������A�댯���̊C��^���Ɋւ��ĉ䂪���ɂ����Ď{�s����Ă����@�K�́A���̂Ƃ���ł������B
�i�A�j�D�����S�@�i���a8�N�@����11���j28���i�댯���̉^�����Ɋւ���Z�p�I��́A���y��ʏȗ߂������Ē�߂�|�K�肵�Ă���B�j
�i�C�j�D�����S�@28���̈ϔC�Ɋ�Â��댯���D���^���y�ђ����K���i����16�N���y��ʏȗߑ�51���ɂ�������̂��́B�ȉ��u��K���v�Ƃ����B�j
��K��2��1���́A�댯���̒�`�K���u���Ă���A������ʼnR�������ނ��댯���Ƃ���A�R�������ނ́A�R�������i�C���ɂ��e�Ղɓ_����A�����A�R�Ă��₷�������ŁA�����Œ�߂���̂������B������i1�j�j�A���R���ΐ������i���R���M���͎��R�����₷�������ŁA�����Œ�߂���̂������B������i2�j�j�y�ѐ������R�������i���ƍ�p���Ĉ��ΐ��K�X�����镨���ŁA�����Œ�߂���̂������B������i3�j�j��3�̂��̂Ƃ���Ă���B
�i�E�j��K��2��1����i1�j�A3��1��4���A2�����̈ϔC�Ɋ�Â��D���ɂ��댯���̉^��������߂鍐���i����15�N���y��ʏȍ�����1616���ɂ�������̂��́B�ȉ��u�덐���v�Ƃ����B�j
�����āA�����̖@�K�̓��e�́A�䂪�����������Ă���u1974�N�̊C��ɂ�����l���̈��S�̂��߂̍��ۏ��v�iSOLAS���j��������VII�͂̓��e�y�т��̉��ō��A�̋��͂ɂ���߂�ꂽ���ۊC��댯���K���iIMDG�R�[�h�j�Ǝ����I�ɓ����e�ƂȂ��Ă���B�Ȃ��A�댯���́A�댯���̎�ދy�т��̐����ɂ�荑�A�ԍ��y�ѐ����i������܂�B
����ɁA�D�����S�@27���́A�u�D���m���q���y�l���m���S��փV����ʒi�m�K��A���g�L�n���m�K���]�t�v�ƋK�肵�Ă���A�����ɂ������ɂ́ASOLAS�����܂܂�A�����́A��7��A����3�K���ɂ����āA�댯���̉^���ɂ���IMDG�R�[�h�ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɩ��L���Ă��邩��A�댯���̉^���ɂ��ẮA��K�����͊덐���ɋK�肪�Ȃ��ꍇ�ł������Ă�IMD6�R�[�h�ɋK�肪����ꍇ�ɂ́A����ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�C NA�[125
�i�A�j���Ȕ����������Y����
�덐��3��1��2���A�ʕ\��1�Ɍf����ꂽ�댯���u���A�ԍ�3226=���Ȕ���������D�i�ő́j�v�ɂ��āA���ʕ\��1���l1�i2�j�́A���w���Ƃ��āu2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[5�|�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�������Ă���i�Ȃ��A���Ȕ����������Ƃ́A�M�I�ɕs����ŁA�_�f�Ȃ�����C�̋������Ȃ��ꍇ�ł����Ă�����Ɏ��ȕ������N�����₷�������������i�b��6�j�B�ȉ������B�j�B
NA�[125�̎�Ȑ����́A2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���ł���A�������̕s�������܂ނ��̂́A����܂�2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���ɂ��ď����ꂽ�����ł͍��A�ԍ�3226�F���Ȕ���������D�i�ő́j�ɕ��ނ���i�b�n8�Y�t���U14���A�b�C14�Ȃ���21�A48�y��49�j�A�⏕�Q���l�_�C�g�[������15�N12���ȑO�y�і{�����̌��NA�[125���댯���Ƃ��Ď�舵���Ă����B
���������āANA-125�́A���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�ő́j�ł��鉻�w���u2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�̂��́j�v���́u���̑��̉��w���v�ɊY������̂ł���A�R�������ނ̂����R�������ɊY������B���̓_�A�u�Z�x��100����%�v�Ƃ́A�H�ƓI���i�itechnically pure substance�j���Ӗ�����Ƃ���ANA�[125�ɐ�߂�댯���̔Z�x��90%���A��%���x�̐������܂ނ���Ƃ����Ċ댯�������������Ƃ͂����Ȃ�����A�H�ƓI���i�ɓ�����B
�Ȃ��A�u�����̊댯���]���̎������@�y�є����v�i����14�N8��21�����C����263����3�ɂ�������̂��́B�ȉ������B�b��7�j�́A���ȉ����������x�i���������ȉ����������N����������̂���Œቷ�x�̂��ƁB�ȉ������B�j���ێ�75�x���镨���ɂ��āA���Ȕ����������Ɣ��肵�Ȃ����ƂƂ��Ă���A�퍐�́ANA�[125�̎��ȉ����������x��ێ�80�x�ł���Ƃ��Ă��邪�A���ȉ����������x�́A���b�g���Ɩ��͐��i���ƂɈقȂ蓾��̂ł��邩��A�{�����̂ŏ�������NA�[125���̂��̂̎��ȉ����������x���ێ�80�x�ł������Ƃ͌���Ȃ��B
�i�C�j���Ȕ��ΐ������Y����
������ЃJ���e�b�N�i�ȉ��u�J���e�b�N�v�Ƃ����B�j�́A����17�N12��14���t���u�댯���A���Ɋւ��鍑�A�����̎����y�щ��w�����̊댯���]���������ʕ��v�i����17�j�ɂ����āANA-125�ɂ��āA�u���Ȕ��M�������ɊY������B�v�Ɣ��肵�Ă���Ƃ���A���Ȕ��M�������Ƃ́A���R���ΐ������i���ʂł����Ă���C�Ɛڂ���5���ȓ��ɔ����镨���i�t�̖��͌ő̂̍������y�їn�t���܂ށj�������B�ȉ������B�j�ȊO�̕����ł����āA��C�Ɛڂ����ꍇ�ɃG�l���M�[�̋����Ȃ��Ɏ��Ȕ��M���₷�������������i�b��6�j�B�덐���ʕ\��1�ɂ����āA�댯���u���A�ԍ�3088:���Ȕ��M�������v�́A�R�������ނ̎��R���ΐ������Ƃ���Ă���B
���������āANA�[125�́A�R�������ނ̎��R���ΐ������ɂ��Y������B
�E PSR-80
�i�A�j���Ȕ����������Y����
�덐��3��1��2���A�ʕ\��1�Ɍf����ꂽ�댯���u���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�ő́j�v�ɂ��āA���ʕ\1���l1�i2�j�́A���w���Ƃ��āu2�[�W���]�[1�[�i�t�g�[���[5�|�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�y�сu2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[�X���z���_�G�X�e��D�i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�������Ă���B
PSR-80�́A�A�Z�g���ƃs���K���[���̏k������1�A2�[�i�t�g�L�m���[�i2�j��W�A�W�h�[5�[�X���z���_�G�X�e���iEster compound
of 1, 2 - Naphthoquinone - (2) - diazido - 5 - sulfonic acid with Pyrogallol-acetone
condensation�j���܂�ł���A���A�ԍ�3226:���Ȕ����������ł��鉻�w���u2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[5�|�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�Ⴕ���͉��w���u2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[�X���z���_�G�X�e��D�i�Z�x��100����%�����̂��́j�v���́u���̑��̉��w���v�ɊY������B���̓_�A�u�Z�x��100����%�v�̈Ӌ`�ɂ����ẮA��L�C�i�A�j�ŏq�ׂ��Ƃ���Ɠ����ł���B
PSR�[80���A���ɏ�L�̂�����ɂ��Y�����Ȃ��Ƃ��Ă��A���A�ԍ�3222:���Ȕ���������B�i�́j�A���A�ԍ�3224:���Ȕ���������C�i�ő́j�A���A�ԍ�3228:���Ȕ���������E�i�ő́j���͍��A�ԍ�3230:���Ȕ���������F�i�ő́j�̂����ꂩ�ɂ͊Y������B�܂��A���{���{�́A����16�N5��25���APSR-80�Ɖ��w��������ł���CAS�ԍ�68584-99-6�̕����ɂ��A���ȉ����������x�ێ�65�x�A�R�������̎��Ȕ���������4.1�����A���A�ԍ�3228�F���Ȕ���������E�Ƃ��Đ\�����A�F�߂�ꂽ�B���A�ԍ�3228:���Ȕ���������E�́A�덐���ʕ\��1�ɂ����āA�R�������ނ̉R�������Ƃ���Ă���i�b�n8�A33�j�B
�Ƃ���ŁA�����̊댯���]���̎������@�y�є����́A���ȉ����������x���ێ�75�x���镨���ɂ��āA���Ȕ������������珜�O���Ă��邪�APSR�[80�̎��ȉ����������x�͐ێ�70�x�ł���̂ŁA��L���O���R�ɂ͍��v���Ȃ��i�b��7�A����3�Ȃ���5�j�B
���������āAPSR-80�́A���Ȕ����������ɊY������B
�i�C�j���Ȕ��ΐ������Y����
�Вc�@�l���{�C�����苦��i�ȉ��u���{�C����苦��v�Ƃ����B�j�쐬�ɌW�镽��17�N3��30���t���댯���]���ؖ����i����16�j�́APSR-80���āA�u"���Ȕ��M�������A�e�퓙���U"��"�Y������"�Ɣ��肷��B�v�ƋL�ڂ��Ă���B�덐���ʕ\��1�ɂ��ƁA���Ȕ��M�������́A���A�ԍ�3088�̊댯���Ƃ���A�R�������ނ̂������R���ΐ������Ƃ���Ă���B���������āAPSR�[80�́A�R�������ނ̂������R���ΐ������ɂ��Y������B
�G �Ȃ��A�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A���Ȕ��M�������̐ݒ艷�x���ێ�100�x�A120�x�y��140�x�ł��邱�Ƃ���A�D�q���̉��x���ێ�10O�x�A120�x����140�x�ɒB���Ȃ���Ύ��Ȕ��M�̔������J�n���Ȃ��Ǝ咣���邪�A���Ȕ��M�������̐ݒ艷�x�́A���Y���������Ȕ��M�������Ƃ��Ă̐�����L���邩�ۂ��f���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�Z���Ԃŏ��ʂ̃T���v���ɂ�鎎���̂��߂Ɏw�肳�ꂽ���̂ɂ������A�D�q���̉��x���ێ�100�x�A120�x����140�x�ɒB���Ȃ���Ύ��Ȕ��M�̔������J�n���Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�i�퍐�̎咣�j
�A �D�����S�@27�������̋K��ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ώۂ́A�D���̊��q���y�ѐl���̈��S�Ɋւ��鎖���ł���A�댯���̉^���Ɋւ������߂�IMDG�R�[�h�ɏ]�����Ƃ܂ł͗v�����Ă��Ȃ��B
�C NA�[125
�i�A�j���Ȕ���������
�����̊댯���]���̎������@�y�є����́A���ȉ����������x���ێ�75�x���镨���ɂ��āA���Ȕ����������Ɣ��肵�Ȃ����ƂƂ��Ă���Ƃ���ANA�[125�́A���ȉ����������x���ێ�80�x�ł���i����6�j�A�ێ�75�x���邽�ߎ��Ȕ����������ɂ͊Y�������A��K���y�ъ덐���̒�߂�댯���ɂ͓�����Ȃ��B
���ɁA���ȉ����������x���ێ�75�x���镨�������Ȕ����������ɓ����蓾��Ƃ��Ă��A�u�Z�x��100����%�̂��́v�ł͂Ȃ��ꍇ�͊�K���y�ъ덐������߂�댯���ɂ͓�����Ȃ��B��K���ɂ��덐���ɂ��A�덐���ʕ\�́u�Z�x��100����%�̂��́v���H�ƓI���i�itechnically pure substance�j���w���Ƃ̋L�ڂ͂Ȃ��A�����̏��x�Ɍ�������̂��Y������Ƃ̋L�ڂ��Ȃ��̂ł��邩��A�u�Z�x��100����%�̂��́v�Ƃ́A�s�������܂܂Ȃ����̂��w���Ɖ����ׂ��ł���B�������A�{���R���e�i�ɐύڂ��ꂽ5000Kg��NA�[125�̔Z�x�́A�����Ƃ�92�D1%�ł���A���Ȃ��Ƃ�7.9%�i395Kg�j���̕s�����y�ѐ������܂܂�Ă����B��������ƁANA�[125�́A�u�Z�x��100����%�̂��́v�ɊY�����Ȃ��B
���Ɍ�����̎咣�̂Ƃ���u�Z�x��100����%�̂��́v���H�ƓI���i�������Ƃ��Ă��A�⏕�Q���l�_�C�g�[���������Ă���NA�[125���܂�ł��鐅���͏��ʂƂ͂����Ȃ��̂ŁANA�[125�͊�K���y�ъ덐���ɂ��鉻�w�����̍H�ƓI���i�Ƃ͂����Ȃ��B
�Ȃ��A�덐���ʕ\�u���̑��̉��w���v�Ƃ́A���ʕ\�ɗ��ꂽ���w���ȊO�̉��w�����Ӗ����Ă���Ɖ�����邩��A���ʕ\�ɗ��ꂽ���w���ŁA�Z�x���قȂ���̂́A����Ɋ܂܂�Ȃ��B
�i�C�j���Ȕ��M������
�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�퍐�ɑ��āA�{�����̑O�ANA-125�͊댯���ł͂Ȃ��Ƃ���������Ă����B���������āANA-125�́A�{�D�ɖ{���R���e�i���D�ς݂��ꂽ���_�ɂ����āA���Ȕ��M���������܂߁A�댯���ɊY�����Ă��Ȃ������B
�E PSR�[80
�i�A�j���Ȕ���������
PSR-80�́A�A�Z�g���ƃs���K���[���̏k������1�A2�[�i�t�g�L�m���[�i�Q�j�|�W�A�W�h�[5�[�X���z���_�G�X�e���Ɛ����y�їn�}�Ƃ��ܗL���������ł���A�{���R���e�i�ɐύڂ��ꂽ400Kg��PSR-80�́A���Ȃ��Ƃ�1.0�Ȃ���1.2%�i4.0�Ȃ���4.8Kg�j�̐������܂݁A���v3.0%�ȉ��i12Kg�ȉ��j�̕s�������܂�ł��āA�Z�x��100����%�łȂ�����A���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�ő́j�̉��w���u2�[�W�A�]�[1��i�t�g�[���[5�[�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�܂��APSR-80�Ɖ��w��������ł���Ƃ����CAS�ԍ�68584�[99�[6�̕����́A����17�N1��25���t�����A�����ɂ����āA���A�ԍ�3228�F���Ȕ���������E�̊댯���Ɏw�肳��Ă��邩��APSR-80�́A���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�ő́j�̉��w���u2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���X���z���_�G�X�e��D�i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�ɊY�����Ȃ��B
����ɁA�P�Ɂu2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�ƔZ�x���Ⴄ�����̕����ł���PSR-80�́A���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�ő́j�́u���̑��̉��w���v�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�������APSR�[80�́A���A�ԍ�3228:���Ȕ���������E�i�ő́j�́u���̑��̉��w���v�ɂ��Y�����Ȃ��B�m���ɁA����16�N9������̊덐���ʕ\��1���l1�i2�j�́u���Ȕ����������̉��w�����v�̕\�̒��ɂ́A����18�N12��5���t���덐�������ɂ�荑�A�ԍ�3228:���Ȕ���������E�i�ő́j�̉��w���Ƃ��Ēlj����ꂽ�u�A�Z�g���[�s���K���[���R�|���}�[2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���|�l�[�g�i�Z�x��100����%�̂��̂Ɍ���j�v�Ƃ����L�ڂ͂Ȃ������̂ŁA�{�����̓����A���A�ԍ�3228�F���Ȕ���������E�i�ő́j�́u���̑��̉��w���v�Ɋ܂܂�Ă����Ƃ��l������B�������Ȃ���A�⏕�Q���l�_�C�g�[�������̔�����PSR�[80�́A�Z�x��100����%�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�A�Z�g���[�s���K���[���R�|���}�[2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z�l�[�g�i�Z�x��100����%�̂��̂Ɍ���j�v�ɊY�������A���������Ă܂��A�u���̑��̉��w���v�ɂ��Y�����Ȃ��B
�i�C�j���Ȕ��M������
�⏕�Q���l�_�C�g�|�́A�퍐�ɑ��āA�{�����̎��̑O��PSR�[80�͊댯���ł͂Ȃ��Ƃ���������Ă����B���������āAPSR-80�́A�{�D�ɖ{���R���e�i���D�ς݂��ꂽ���_�ɂ����āA���Ȕ��M���������܂߁A�댯���ɊY�����Ă��Ȃ������B
�i�⏕�Q���l�_�C�g�[�̎咣�j
�A NA-125�́A50Kg�̗A�����ɂ����鎩�ȉ����������x���ێ�80�x�ł���A�ێ�75�x���邱�Ƃ���A���Ȕ����������ɊY�����Ȃ��B
�܂��ANA�[125�́A6�Ȃ���7%�̐������܂�ł��邲�Ƃ���A�덐���ɂ����č��A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�ő́j�̉��w���u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�ɊY�����Ȃ��B����ɁANA-125�́A���Ȕ����������ɓ�����Ȃ��ȏ�A�u���̑��̉��w���v�ɂ��Y�����Ȃ��B
�C�i�A�j PSR-80�́A�덐���ʕ\��1���l1�ɂ����ĕ\������Ă���댯���ɊY�����Ȃ��BPSR�[80�́A�G�X�e���������Ɛ����y�їn�}�Ƃ��ܗL���Ă��鏤�i�ł���̂ŁA�덐���Ŏw�肳��Ă���u�Z�x��100����%�̂��́v�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�܂��APSR�[80�́A���h�@��̊댯���ɊY�������A����14�N2�����납��n�܂����c�Ƃ�X�ł̊C��A����24��𐔂��A�{�����̎��Ɠ��l�̎菇�ŕ⏕�Q���l�_�C�g�[����퍐�ɔ̔����ꂽ��ɁA�퍐�ɂ��C��A��������Ă����ɂ�������炸�A�Ђ݂̂Ȃ炸�A����i���N���[�����Ă��Ȃ������i�Ȃ��APSR-80�́A�����Ԉ��̍������ɒu���ꂽ�g���A�Ђ̌����Ƃ͂Ȃ�Ȃ����i���̗��N����B����Ɉ��̉��x������Ԃň�莞�Ԓu���ꂽ�g���ɁA���ȉ����������N�����Ђ̌����ƂȂ邱�Ƃ�����B�j�B
���������āAPSR-80�́A���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�Ƃ��Ċ덐���ʕ\��1���l1�Ɏ�����Ă���댯���ɂ͊Y�����Ȃ��B
�i�C�j�����Ƃ��A�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�{�����̂������������Ƃ��āAPSR-80�����Ȕ����������Ƃ��Ď�舵�����ƂƂ����B�������A���̎戵���́A�O���܂�PSR�[80�ɂ��Ă̎Г��I�Ȏ戵���Ƃ��āA���A�ԍ�3226����3228�ɑ���������̂Ƃ��Ď�舵�����ƂƂ����ɂ������APSR�[80���덐���ʕ\1���l1�ɋL�ڂ���Ă���댯���ɊY�����邱�Ƃ𗝗R�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��B
�i�E�j������́A�W�A�]�������ł���A�����Ƃ��Ď��Ȕ����������Ƃ��Ă̊댯����L���邱�Ƃ͈�ʂɒm���Ă���̂ŁA�퍐�́A���̊�K����̊댯���Y�������^���A���O�Ɏ��Ȕ����������ɊY�����邩�ۂ��肷��`��������Ǝ咣���Ă���B
�������A�W�A�]�������́A�I�t�B�X�⌚�z����̐Ă��Ƃ��Ďg�p����Ă������ɓh�z����Ă������̂��܂܂�A�W�A�]������������Ƃ����āA��ʓI�Ɋ댯���Ƃ͍l�����Ă��Ȃ��BPSR�[80���A����p�����ޗ��Ƃ��ėp��������̂ł���A�ʏ�͊댯���ł���ƔF�������ׂ������̂��̂ł͂Ȃ��B������̏�L�咣�͉��w�I�������������̂ł���B
�E �{���e�ݕ��́A���Ȕ��M�������ł͂��邪�A���R���ΐ������ł͂Ȃ��B
�{���e�ݕ��̎��R���ΐ������y�ю��Ȕ��M�������̎������ʁi����16�A17�j�ɂ��A�{���e�ݕ��͂�������A���R���ΐ������ɂ͊Y�����Ȃ��B
�i2�j���_2�i�{�����̂̌����j
�i������̎咣�j
�A �{�����̂̌����́A�{���e�ݕ������ȕ������N���������Ƃɂ���B
�i�A�j�{���R���e�i�����ɂ����āANA�[125�́A�����ɂ܂Ƃ߂Đςݕt�����APSR-80�́A���̉��ɕ���ł܂Ƃ߂Đςݕt�����Ă����B�������A�{���R���e�i�ɂ́ANA-125��5000Kg�APSR�[80��400Kg�Ƃ�����e�ʂ��ANA�[125�ɂ��Ă�50Kg�̃t�@�C�o�[�h����100�ɁAPSR�[80�ɂ��Ă�10Kg�̃J�[�g��40�ɁA���ꂼ����[����Ă����B���̗e�ʂ��炢���āA�����́A�{���R���e�i���ɁA3�Ȃ���4�i�ɐςݏグ���Ă���A�܂��A�{���R���e�i���̑啔�����̂���`�ŁA���[����Ă����͂��ł���B���̕����e�ʂƐϕt��Ԃ̃X�P�[���A�b�v���ʂɂ��A�����̊O�\�ʐς͋��߂��M�������ɂ����ɂ������B�{���e�ݕ��́A����������Ԃ̂܂ܖ{���R���e�i�Ɏ��[���ꂽ���̂ł���A�ۗ�R���e�i�Ɏ��[����Ȃ��������߁A�l�X�Ȉ��e�������\��������B
�����āA�{���e�ݕ��̈ꕔ�����ŏ��Ɏ��ȕ������͔��M�������J�n���A���ꂪ���͂ɍL����A�{���e�ݕ��S�̂��M�\���̌��E���x�ɒB���Ď��ȕ����������N�����Ɏ������B
�i�C�j���ȉ����������x�́A���b�g���Ɩ��͐��i���ƂɈقȂ蓾��̂ŁAPSR�[80�̎��ȉ����������x����ɐێ�70�x�ł���Ƃ͌��炸�ANA-125�̎��ȉ����������x����ɐێ�80�x�ł���Ƃ�����Ȃ��B����PSR-80�̎��ȉ����������x���ێ�70�x�ł���ANA�[125�̎��ȉ����������x�͐ێ�75�x���Ă���Ƃ��Ă��A���Ȕ����������͕����̏W�ςɂ��~�M����̂ŁA���ȉ����������x�����Ⴂ���x�Ŏ��ȕ������J�n���邱�Ƃ͂��蓾��B
�i�E�j�܂��A���Ȕ��M�������́A�ێ�100�x�ɒB���Ȃ��Ă����Ȕ��M�������J�n���邨����̂��镨���ł���A�{���e�ݕ��͎��Ȕ��M�������N�������\���������B���Ȕ��M�������́A��C�i�_�f�j�ɎN����Ă������A�_���ɂ���Ď��Ȕ��M��������B���Ȕ��M�����������Ȕ����������ł�����ꍇ�A���M���x�����M���x������Ɓi���M���x�����M���x�j�A����ɒ~�M���x���㏸���Ă����A�₪�Ď��ȕ������N�����Ă��ꂪ���ւƔ��W���Ă������ƂɂȂ�B
�����āA�{���e�ݕ��́A���Ȕ��M�����������Ȕ����������ł���A���̂��߁A���Ȕ��M�����ɂ��~�M���x�����Y�����̎��ȕ������J�n���鉷�x�ɒB����ƁA���ȕ������J�n����B���̗g���A�O������̔M�̋������Ȃ��Ƃ�����̔��M���ʂƒ~�M���ʂ����ւ��āA���ȕ������J�n�����Ԃɂ܂ʼn��x�����߂�B
���́u���M���x�����M���x�v���ۂ́A�O���v���A���ɊO������M���������邱�ƂɂȂ�i�Ⴆ�A�{���ɂ����鍶����3�R�����^���N����̔M�j�A���i�����ƍl�����A�{�D�̑�3�D�q�ꕔ�ɂ����āA�{���R���e�i�ɑ��āA����ɖʂ��ĉ��M��Ԃɂ�����������3�R�����^���N�̉��x���A�{�����̔����܂�55���Ԃقlj�����ꂽ���Ƃ́A�{���e�ݕ��̊댯�����݉��̑��i�v�f�ƂȂ����\��������B
�i�G�j����16�N10��20�������A�R���e�i�̉��x�����x�܂ŏオ��A�܂��A���x�̎��ɖ{���e�ݕ����������̂��A���m�ɒ��ׂ邱�Ƃ͕s�\�ł��邪�A�œK�|���v�ڑ����x���ێ�35�x�ł��邱�Ƃ���A������3�R�����^���N���̔R�����́A���Ȃ��Ƃ��ێ�30�Ȃ���40�x�ɉ��M����Ă����ƍl�����A�ێ�60�x���x�ɉ��M����Ă����\�����r���ł��Ȃ��Ƃ���ł���B
�i�I�j���������āA�{���e�ݕ��̎��Ȕ��M�����y�т���ɂ��X�P�[���A�b�v���ʓ��ɂ��~�M�ɂ�莩�ȉ��M�������A�����Ɏ��Ȕ������������鐫����L���邪�̂ɁA�{���e�ݕ��̗��҂��A���͂��̈���A�M�\���̌��E���x�ɒB���A����Ȏ��ȕ����Ɏ������Ƃ���̂������I�ł���B
���̂悤�ɁA�{�����̂́A�{���e�ݕ����͂��̂ǂ��炩�̎��ȕ����������Ƃ�����̂ł���B
�C �i�A�j����ɑ��A�퍐�́A�{���R���e�i���̃t�F���g�y������R�o�����K�X�ւ̈����A�{�����̂̌����ł���ȂǂƎ咣���邪�A�t�F���g�y�������݂������Ƃ͏\���ɗ�����Ă��Ȃ����A�퍐���s���������͐M�p�ł��Ȃ��B
�i�C�j�܂��A�퍐�́A������3�R�����^���N�y�т��̕t�߂̉��x�������ł��������Ƃ��w�E���āA������3�R�����^���N�́u���v���{�����̂̌����ł���Ǝ咣���邪�A����16�N10��20���ߑO6���ɂ����āA��3�R�����^���N�̉t�ʂ�3.1m�ł��������Ƃ��m�F����Ă���A�u���v�̏�Ԃ͐����Ă��Ȃ��B��L�̍����̌����́A����19���ߌ�11��55���ȑO�̒i�K�Ŋ��ɔ������Ă����{���e�ݕ�����̔��M�ɂ���ƍl������B
�i�E�j����ɁA�퍐�́A������3�R�����^���N���̔R�����̉��x���ێ�92�x�ɒB���Ă����Ǝ咣���邪�A���ɔR�������M�p�C�v�ɑS�e�ʂ̏��C����������ō��̉��M��Ԃł������Ƃ��Ă��A�{���R���e�i�̒����̉��x�́A�ێ�72.5�x������̂ł͂Ȃ��i�b�n43�j�A�R�����̉��x���ێ�92�x�ɒB���Ă������Ƃ��������킹��q�ϓI���������Ă��Ȃ��̂ł����āA�ێ�92�x�Ƃ������l�́A�R�����̖����v���{�����̂ɂ����A���������x�\�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃɂ����̂ƍl������B�����āA���������R���e�i�D�̑D�q���̉��x�ɂ��ẮA���x�ɐݒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̋K��͂Ȃ�����A���ɁA�퍐���咣����悤�ɍ�����3�R�����^���N�̋�����������A���^���N���̔R�����̉��x���ێ�92�x�ł������Ƃ��Ă��A�ӔC�����ɉe�����Ȃ��B
�i�퍐�̎咣�j
�A �{���R���e�i�̉��̕����ɐςݕt�����Ă����ݕ����قƂ�Ǒ��Q�����Ă��Ȃ����Ƃ���APSR�[80�́A�{���R���e�i�����ɂ����āANA�[125�̏�ɐςݕt�����Ă����ƍl������B
�C NA�[125�̕����J�n���x�͐ێ�143�x�A���ȉ����������x�͐ێ�80�x�Ƃ���A�܂��APSR�[80�̕����J�n���x�͐ێ�131�x�A���ȉ����������x�͐ێ�70�x�ł���B���ȉ����������x�̒�`�ɏƂ炵�āA�{���e�ݕ������ȉ����������x�����Ⴂ���x�Ŏ��ȕ������N�������Ƃ͂Ȃ��B
�����ŁA��ʂɁA�D�q���̉��x�͔M�ъC����܂ލq�H�ł��ێ�35�x���x�ł���A�D�q���ɐςݕt����ꂽ�R���e�i�����̉��x�ω��́A�ɂ߂Ċɂ₩�ŏ������A�O���̉��x�ω��Ɋɖ��ɒǏ]����B���ȉ����������x�𑪒肷�邽�߂̒~�M���������́A���w������50Kg�̕�`�Ԃɍ���ꂽ�Ƃ��Ɠ�����Ԃɒu�����̂Ƃ���邪�APSR�\80��10Kg�̕�`�Ԃɓ�����ANA�[125��50Kg�̕�`�Ԃɓ�����Ă����B
���̂悤�ɁA�{���e�ݕ��́A�~�M���������̊��������M���₷���A���A�~�M���ɂ��������ɒu����Ă����B
������́A�{���e�ݕ������ȕ������N�������߂ɕK�v�ȉ��x�y�ю��ԕ��тɖ{���e�ݕ����������̂悤�Ȋ����ɒu����Ă����������咣�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A���m�Ȏ咣���͂���Ă��Ȃ��B���ɖ{���e�ݕ��̒����̉��x�����ȉ����������x��荂���ł������̂ł���A������3�R�����^���N�̉ߔM�Ƃ����{�D���̎���ɂ����̂Ɛ��F�����̂ł���A�퍐�ɋA�Ӑ��͂Ȃ��B
�E �{���e�ݕ��͍H�Ɛ��i�ł���A�ʏ�A���ȉ����������x�����i���̓��b�g���Ƃɑ傫���قȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B��������ƁANA�\125�̎��ȉ����������x�͐ێ�75�x���������A�܂��APSR�[80�̂���͐ێ�70�x�Ƃ����̂ł��邩��A�{���e�ݕ������ȕ������N�������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B���ɁA�{���R���e�i�����̉��x���ێ�60�x�߂��ɂȂ����Ƃ��ăJ���APSR�[80�����ȕ������N�������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B�܂��A�ʏ�̍q�s�ŃR���e�i���ɐێ�60�x�ȏ�̍�����������Ƃ͍l�����Ȃ��B��������ƁA�{���R���e�i����3�D�q�ɐύڂ��ꂽ���Ƃ��{�����̂̒��ڂ̌����Ƃ͍l�����Ȃ��B
�G �{�����̂̌����́A���̂����ꂩ�A���͗��҂������������Ƃɂ��B
�i�A�j�{���R���e�i���ɁA�ϕt�\�ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��t�F���g�y��1200�{����̒i�{�[�����������݂��Ă����B�{���R���e�i�������A������3�R�����^���N�̉��M�i��L�i�C�j�̌�������M���܂ށB�j�̉e���ɂ��A�����ƂȂ�A�{���R���e�i�̑O���ɐςݕt�����Ă����t�F���g�y������R���K�X���������A�R���K�X���{���R���e�i�̒ꕔ�ɑؗ����Ĕ��������C���\�����A�{���R���e�i���̉ݕ��̍���ނ̖��C�ɂ���Ĕ������ؗ������Ód�C���X�p�[�N���āA���������C�Ɉ����Ĕ������A�{���e�ݕ��Ɉ������\��������B
�i�C�j�{�����̂́A����16�N10��20���ߑO0��20������ɁA�{�D�D�����A����đ�3�R�����^���N�̉��x��ێ�92�x�܂ʼn��M�������Ƃɂ��A������3�R�����^���N�̊O�ǁi�{���R���e�i�̒�ʋy�э������ʂ���10�Ȃ���15cm�̋�����Ŗʂ��Ă���B�j�����������Ԑێ�10O�x����ُ�ȍ����ƂȂ�A�{���R���e�i������������ԂƂȂ��āA�{���e�ݕ����������\��������B
���̂��Ƃ́A�����ߑO3��18���A��g�����b���ʘH�̍�����3�R�����^���N�����Ɍ������A���x�𑪂����Ƃ���A�uvery
hot�v�ł��������ƁA���̌�A�����ߑO4���ɊC�����U�z����A�����ߑO5���ɃV���N�g�E�V�T�[���q�C�m�i�ȉ��u�ꓙ�q�C�m�v�Ƃ����B�j�������ʼn��x�𑪂����Ƃ���A�ێ�70�x�ł��������Ƃ�������t�����Ă���B
�܂��A�{�D�̍�����3�R�����^���N�ɐύڂ��ꂽ�R�����́A�����_���ێ�35�x�Ƃ����ł��S���̋����R���ł��邽�߁A�@�֎��Ɉڑ����邽�߂ɉ��M���Ȃ���Ȃ炸�A�Œ�ł��ێ�40�Ȃ���45�x�A�����ɂ͐ێ�50�x�ȏ�ɉ��M���邱�Ƃ��H�ł͂Ȃ������B�����āA�����A������3�R�����^���N�̔R�����̉��x�Z���T�[�́A�s��ɂ��ێ�30�Ȃ���33�x�������Ă������߁A�K�v�ȏ�ɉ��M�������Ƃ����F�����B
�i�⏕�Q���l�_�C�g�[�̎咣�j
���Ȕ��M�������́A����������ێ�100�Ȃ���140�x�̍P���������ɒ݂艺���A24���ԘA�����ĕ����̉��x�𑪒肷����e�̎����ł���A������ێ�100�Ȃ���140�x�̊����ɒu�����ꍇ�́A���Y�����̉��x�㏸���v��������̂ł��邩��A���Ȕ��M�������ł���{���e�ݕ����A�{�����̂Ɗ֘A����L����Ƃ������߂ɂ́A�D�q���̉��x���ێ�100�Ȃ���140�x�ɂ܂ŏ㏸���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ�B�������A������́A�D�q���̂��̂悤�ȉ��x�㏸�ɂ��āA���̉\����ے肵�Ă��邱�Ƃ���A�{���e�ݕ��́A�{�����̂̌����Ƃ͖��W�ł���B
�i3�j���_3�i���ΐӔC�@�̓K�p�̗L���j
�i������̎咣�j
���̂Ƃ���A�{�����̂ɂ��Ď��ΐӔC�@�̓K�p�͂Ȃ��B
�A ���ΐӔC�@�́A��襂ȍ��y�ɖؑ��Ɖ������W����䂪���̌����\���A�s�s�\���̓��ꐫ�ɂ��݁A���ɂ��ޏĔ�Q��V�Ђ̔@��������`���I�Ȋ��K��w�i�ɂ��A���Ύ҂ɗ\�������Ȃ�����ȑ��Q�ɂ��Ă͂��̐ӔC�����肵�悤�Ƃ�����̂ł����āA�ɂ߂ēy�����̍������{�ŗL�̖@���Ƃ����A���̓K�p�͈͓͂��{�����Ŕ����������Ɍ�����Ƃ����ׂ��ł���B����āA���{���O�Ŕ��������{�����̂ɂ��Ď��ΐӔC�@�̓K�p�͂Ȃ��B
�C �܂��A���ΐӔC�@�ɂ����u���v�Ƃ́A�u�����V�J�m�P���i���R�č�p������������ŘԃZ�V���^���ꍇ�v�������A�u�R�āv�Ƃ́A�_�����ۂł��艊���B����ɑ��āA�{���e�����͎��ȕ����ɂ��A�_�f�̋������Ȃ��Ă����M�y�ѕ�������̂ł����āA�_�����ۂł���R�ĂƂ͈قȂ�A��������Ȃ��B�ނ���A���ȕ����ɂ�蔭�����钂�f�͔R�Ă�W���̂ł��邩��A�R�č�p�Ƃ͋t�s���鉻�w�����ł���B���������āA�{���e�ݕ��̎��ȕ����́A�Η͂̒P���Ȃ�R�č�p���鎸�Ƃ͂����Ȃ��B
�E ����ɁA�u���v�́A���Ζ̔�����p�ɂ�鑹�Q���܂܂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�{�����̂̔��������ł���{���e�ݕ��́A���̎戵���ɍ��x�̒��Ӌ`�����ۂ����댯���ł���B�{���e�ݕ����A�����ɂ�葽�ʂ̒��f�K�X�A�M���o���̂ł����āA�{�����̂́u�����v�ɊY��������̂ł���B���̂��Ƃ́A�{���R���e�i�̑��ʂ��O�Ɍ������Ėc��A�T�����ė����t���Ă������Ƌy�і{���R���e�i���Ɏ��[����Ă������̑��̍��ډݕ��������̏�ԂŎc�����Ƃ����{�����̌�̏Ƃ����v����B�Ȃ��A�����Ƃ����鎩�ȕ����ɂ�鍂�M���ЂւƔ��W�����Ƃ��Ă��A���̉Ђɂ���Đ��������Q�ɂ��āA���ΐӔC�@�̓K�p�͂Ȃ��B
���������āA�{�����̂ɂ͎��ΐӔC�@�̓K�p���Ȃ��B
�i�퍐�̎咣�j
���̂Ƃ���A�{�����̂ɂ͎��ΐӔC�@���K�p�����B
�A ���ΐӔC�@�ɂ͓K�p�͈͂���{�����Ŕ��������ЂɌ���|�̕����͂Ȃ�����A���R�ɓ��{���O�Ŕ��������Ђɂ��K�p�����B
�C ���ΐӔC�@�̗��@��|�́A��1�ɁA���l�����Ȃ̍�����Ŏ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ�ӂ�Ȃ��̂ł���A���̏ꍇ�ɂ͎��Ȃ̍������Ď����邽�ߗG�����ׂ��������g�������Ȃ��Ȃ����ƁA��2�ɁA�l�Ƃ����W����ꏊ�Ŏ������ꍇ���̑��Q�͍L�͈͂ɋy�ї\���ł��Ȃ��̂ł���A���Ύ҂ɗ\���s�\�ȑ��Q�̔����ӔC�S�����邱�Ƃ͍��ł��邱�Ƃɂ���B
�{���ł��A�퍐�́A���Ȃ̍�����Ŏ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ�ӂ�Ȃ��������A�{�����̂ɂ��{���e�ݕ����������Ă���A�G�����ׂ�����F�߂���B�܂��A�{�D�̂悤�ȉݕ������W����R���e�i�D�Ŏ������ꍇ�ɂ́A���̑��Q�́A���ɍL�͈͂������̉ݕ��ɋy�Ԃ��߁A���Q�͈̔͂͗\���s�\�ł���B���ہA������̐������z�̑��z�́A���݁A��11���~�ȏ�̋��z�ɂ̂ڂ��Ă���B���ɁA�{�����̂��퍐�̎��ɂ��Ƃ��Ă��A���̑��Q�̔����ӔC��S���퍐�ɕ��킹�邱�Ƃ͐r�����ł���B���̂悤�ɖ{���͎��ΐӔC�@�̎�|���Ó�����T�^�I�ȏꍇ�ł���A���ΐӔC�@���K�p�����ׂ��ł���B
�E ������́A�{�����̂̌����́A���ȕ����ł����āA�_�����ۂ≊������������̂ł͂Ȃ�����A�Η͂̒P���ȔR�č�p�ł���u���v�ɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ��A�܂��A�Ђ̌������A�Ζ�A�K�X�ނƂ������戵�҂ɍ��x�̒��Ӌ`�����ۂ������̂̔����ɂ��Ƃ��ɂ́A���ΐӔC�@�̓K�p���Ȃ��Ƃ���Ă���̂Ɠ��l�A���ɖ{�����̂ɂ����ĉЂ��������Ă����Ƃ��Ă��A���ΐӔC�@�̓K�p�͂Ȃ��Ǝ咣����B
�������A�{���e�ݕ������ȕ������N�����A����Ɏ_�f�̋���������Ȃ������Ƃ��Ă��A����̕��q���ɂ���_�f�ɂ��_�����ۂ͔F�߂��邵�A�����R�Ă����݂���B�܂��A�{���e�ݕ������ȕ������N�������Ƃ��Ă��A���ꂪ�u���̂��̂ňꎞ�ɑ�ʂ̃K�X�A�M�����o�����Ƃ������Ƃ͂Ȃ�����A�����ɂ͓�����Ȃ����A�{���e�ݕ��́A�Ζ��K�X�̂悤�Ȋ댯���ł͂Ȃ��B����ɁA�퍐�́A�{���e�ݕ��̐����A�̔��A����͖{'���R���e�i���ւ̐ϕt���Ɋ֗^���Ă��Ȃ��B�����Ԃ��āA������̎咣�͎����ł���B
�i�S�j���_4�i�퍐�̉ߎ����͏d�ߎ��̗L���j
�i������̎咣�j
�퍐�ɂ́A�{�D���ɑ��āA�{���e�ݕ����댯���ł��邱�Ƃ̒ʒm����ӂ����ߎ�������B���ɁA�{�����̂Ɏ��ΐӔC�@�̓K�p������Ƃ��Ă��A�퍐�̉ߎ��͎��ΐӔC�@�ɂ����d�ߎ��ɓ�����Ƃ����ׂ��ł���B
�A �퍐�ɂ͖{���e�ݕ��̊댯�����\���\�ł���������
�i�A�j�퍐�́A�W�A�]�������ɂ��Ẳ��w���i�̐����A�댯�����̏����W��g�D��L���Ă��邩��A�{���e�ݕ��̐�����n�m���Ă����B�܂��A�퍐�́A�⏕�Q���l�_�C�g�[�Ƌ��ɁA��������PSR�[80�̊������x�̒����̂��߂̃�����̐ݒ蓙�����肷��Ȃǂ��Ă����B���̂悤�ɁA�퍐�́A�{���e�ݕ��̊댯����F�������邾���̐��m����L���Ă����B
�i�C�j�퍐�y�ѕ⏕�Q���l�_�C�g�[�́A����15�N12���ȑO�ANA�[125���댯���i���Ȕ����������j�Ƃ��Ď�舵���Ă����B
�i�E�j�퍐�́A�{���e�ݕ����W�A�]�������ł��邱�Ƌy�уW�A�]�����������q���ɃW�A�]����܂ޕ����ł��邱�Ƃ𗝉����Ă����B
�W�A�]�������A���ɁA���ʂ̕��q�\���i1�A2�|�i�t�g�L�m���[2�[�W�A�W�h�[5�[�X���t�H�j����j���܂ރi�t�g�L�m���n�����ނ����ȕ������N�����₷���A�����ɂ���ĔM���������鉻�w�����ł��邱�Ƃ́A�����ނ���舵���ƊE�ɂ����Ă͋��ʂ̔F���ł���B�x���Ƃ��⏕�Q���l�_�C�g�[����퍐�ɑ��āuPSR-80�̉^�����@�ɂ��āv�Ƒ肷��d�q���[���i�b��84�j�����t���ꂽ����15�N4��14�����_�ŁA�퍐�́A�{���e�ݕ����W�A�]�������ł��邱�Ƃ�e�ՂɔF�����邱�Ƃ��ł����B
�i�G�j�퍐�́APSR�[80�̉��w����F�����Ă����̂ł��邩��A�덐���ʕ\��1���l1�i2�j�̕\���m�F����A���̕\�����w���̗��Ɂu2�|�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v���f�����Ă���APSR�[80�����Ȕ����������ɊY������\�������邱�Ƃ�e�ՂɔF���������B
�C �퍐�Ɋ댯�����ދ`���i�\���`���j�����邱��
�i�A�j�퍐�́A�{���e�ݕ��̕����ɂ��Đ��I�m����L���Ă������Ƃɂ��݂�A�ב��l�Ƃ��āA�{���e�ݕ��̊C��^�����˗�����ɓ�����A���̊댯���Y�����𐳊m�ɁA�����A�����Ɋm�F���A���f���ׂ����x�̒��Ӌ`�����Ă����B
�i�C�j�D�����S�@27���Ɋ�Â��댯���̗A���ɓK�p�����IMDG�R�[�h�́A���Ȕ����������̗�Ƃ��āA�W�A�]�j�E�����idiazonium salts�j�������i2.4.2.3.1.2�j�AIMDG�R�[�h����߂鎩�Ȕ������������ǂ����́A���A����߂�}�j���A����2�͂̕��@�ɂ��댯���]�������ɂ���Č��肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��߁i2.4.2.3.3�j�A�댯���̕��ނ́A�ב��l����IMDG�R�[�h�ɖ��L���ꂽ�K�Ȍ����̂���@�ւɂ�肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���i2.0.0�j�B����āA�댯�����ދ`���́A�ב��l�ɉۂ���ꂽ�@�ߏ�̋`���ł���B
�������ANA�[125�Ɋւ��ẮA�{�����̑O�Ɋ댯���]�����������{���ꂽ�̂ł��邩��A�퍐�́A�{�����̑O�ɓ��{�C�����苦��̎����@�ւɑ��Ĉ˗�����A�댯���]�������̎��{���\�ł��邱�Ƃ�F�����邱�Ƃ��ł����B���ہA�x�m�t�C����������Ђ́A�Z�x������PSR-80�Ɠ������w�����iacetone-pyrogallol copolymer 2-diazo-1-naphthol-5-sulphonate�j�ɂ��āA�댯���]�������̎��{���˗����Ă���B
�퍐�́APSR�[80�̕���8�N�̉��w�������S���f�[�^�V�[�g�i�ȉ��uMSDS�v�Ƃ����B�j�̍��A�ԍ����ł���A��MSDS�ɂ��⏕�Q���l�_�C�g�[���A�퍐�ɑ��āAPSR�[80�͊댯���ɊY�����Ȃ��Ƃ�����������̂ŁA�퍐�Ƃ��Ă͓��Y����M�����Ă����Ǝ咣����B
�������A�댯�����ދ`�����ۂ���ꂽ�ב��l�ł���퍐�́A�댯�����ދ`����s�����ĊC��^�����ϑ�����ӔC������B�܂��APSR-801�ɂ��āA�⏕�Q���l�_�C�g�[���A�퍐�ɑ��A�ϋɓI�Ɋ댯���ł͂Ȃ��Ɠ`�������Ƃ�A�퍐�ƕ⏕�Q���l�_�C�g�[���APSR-80�ɂ��Ċ댯���ł��邩�ۂ��̘b�������������Ƃ͂Ȃ��B����ɁAPSR�[80�̕���8�N��MSDS�̍��A�ԍ����Ƃ���Ă��邱�Ƃ̈Ӗ��ɂ��āA�퍐���⏕�Q���l�_�C�g�[�ɑ��Ċm�F�������������F�߂��Ȃ��B���ɔ퍐�ɂ����ĕ⏕�Q���l�_�C�g�[������ꂽ���������M�p�����Ƃ̎���������Ƃ��Ă��A����͖O���܂Ŕ퍐�y�ѕ⏕�Q���l�_�C�g�[�Ԃ̖��ɂ������A�퍐���ב��l�Ƃ��Ă̐ӔC��Ƃ�闝�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�i�E�j����āA�퍐�ɂ͊댯�����ދ`���i�\���`���j�ᔽ������B
�E �퍐�������Ă������Ӌ`���i���ʉ���`���j�̓��e�y�т��̜��
�i�A�j�ב��l�̊댯���\���`���A�댯���������̒�o�`�����댯���̊C��^���ɂ����ẮA��K���y�ъ덐����A�ב��l�ɑ��āA�e��ւ̕W�D���y�ѕi�����̕\���`���i��K��8��1���A�덐��7����2�A7����3�j�A�R���e�i��4���ʂւ̕W����t����`���i��K��24���A28��1���j���тɑD�����L�Җ��͑D���ɑ���댯�������Ȃ����R���e�i�댯�������̒�o�`���i��K��17��1���A�덐��14����3��1���A��K��30��1���A�덐��16����3�j���ۂ����Ă���B����āA�퍐�́A�R���e�i�댯���������쐬���Ă����{�D�̑D�����L�Җ��͑D���ɒ�o���ׂ��`���y�їe��ƃR���e�i���̂��̂̊O�����ʂ�4�ʂɊ댯���ł��邱�Ƃ������X�e�b�J�[�i�W�D�j��t���ׂ��`�����Ă����B
�i�C�j�댯���̐ύڕ��@�y�ѐϕt�ʒu���Ɋւ���`��
���Ȕ����������y�ю��R���ΐ������́A�덐���ʕ\��1���ޗ��́u�R�������ށv�ɕ��ނ���A�R�������ނɂ��ẮA���̐ύڕ��@�Ƃ��āA�u���Ό��ƂȂ�ݔ��y�єM�����琅��������3m�ȏ㗣��Ă���A���A�ł�����艷�x�̒Ⴂ�ꏊ�ɐύڂ��邱�Ɓv���v�������i��K��63���A�덐��20����3��1���j�B�܂��A�덐���ʕ\��1�ɂ����āA���Ȕ����������̐ύڕ��@�́uD�v�Ƃ���A���q�D�ȊO�̑D���ɂ��ẮA�u�b��ύځv���v�������i�덐���ʕ\��1���l7�j�B���R���ΐ������Ɋւ��Ă��A�덐���ʕ\��1�ɂ����āA�ύڕ��@�́uC�v�Ƃ���A���q�D�ȊO�̑D���ɂ��ẮA�u�b��ύځv���v�������i�덐���ʕ\��1���l7�j�B���������āA�퍐�́A�{���e�ݕ��ɂ��āA�u���Ό��ƂȂ�ݔ��y�єM�����琅��������3m�ȏ㗣��Ă���A���A�ł�����艷�x�̒Ⴂ�g���ɐύڂ��邱�Ɓv�y�сu�b��ύځv���v������Ă����B
�܂��AIMDG�R�[�h7.1.1.15�́A�u����댯���̂��߂ɁA�M������̕ی삪�v�������ꍇ�ɂ́A�M���ɂ́A�ΉԁA���A�X�`�[���E�p�C�v�i���C�ǁj�A�q�[�e�B���O�E�R�C���i�M���j�A���M�����R�����y�щݕ��^���N�̏�ʋy�ё��ǁA�@���u�ǂ��܂܂��B�v�ƋK�肵�Ă��邩��A�덐��20����3��1���ɂ����u�M���v�ɂ́A�R�����^���N�̏�ʋy�ё��ǂ��܂܂��B
�������A�퍐���ב��l�ɉۂ���ꂽ�댯���\���`���y�ъ댯���������̒�o�`����ӂ������Ƃɂ��A�{���R���e�i�́A��K���y�ъ덐����̐ύڕ��@�ɔ����āA�b���ł����3�D�q���A�������M���ł��鍶����3�R�����^���N�����15cm��������Ă��Ȃ��ʒu�ɐύڂ��ꂽ�B
�i�E�j����
���̂悤�ɖ{���e�ݕ��̐ύڂɂ��ẮA���������L�i�A�j�y�сi�C�j�̊댯���A���y�ђ����Ɋւ�����@�I�K���ɔ����Ă����Ƃ���A���@��̋`���ᔽ�s�ׂł����Ă��A���@��̖��@709���̕s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������ɂ�����u�ߎ��v���\������Ƃ����ׂ��ł���B
�i�G�j�\���`���y�ю��m�O��`��
���ɁA�{���e�ݕ����댯���ɊY�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�{���e�ݕ��̓W�A�]����܂s����ȕ����ł���A�퍐�͖{���e�ݕ��̐�����n�m���Ă����̂ł��邩��A��K���Ƃ͕ʂɁA�^�����ϑ�����ɐ旧���Ė{���e�ݕ��̊댯�����ז���ЁA�C��^���l�A�D�����C��^���ɏ]������҂ɐ\�����A���m�O�ꂷ�ׂ��@����̍�`�����Ă����B
����ɁA�퍐�͏�L���m�O��`���𗚍s������ŁA���S�ȗA�����m�ۂł���悤�ɒ��ӂ�s�����ׂ��`���S���Ă����̂ł����āA��̓I�ɂ͊C��^���l���͑D���ɑ��ĉ^���������Ă���邩�ۂ��₢���킹�A��g���̐����y�ѐg�̂͂��Ƃ��A�^���D���̑D�̖��͐ςݍ��킹�ݕ��ɂ���Q���y�ςȂ��悤�^�����@�y�ѐϕt�ʒu�ɂ��ĊC��^���l���͑D���Ǝ��O�ɑł����킹�A���Q�̔����𖢑R�ɖh�~���邽�ߍőP�̒��ӂ�s�����ׂ��`�����Ă����B
�������A�퍐�͂��̂�����̋`�������ӂ����B
�G �퍐�Ɍ��ʉ���\��������������
�퍐���A�{���e�ݕ��ɂ��A����炪���Ȕ����������Ȃ������Ȕ��M�������ł��邱�ƂɊ�Â��āA�ב��l�ɉۂ���ꂽ�`���ł���W�D���y�ѕi�����̕\�����͊댯�������Ⴕ���̓R���e�i�댯�������̒�o���s���Ă���A�^���l�́A�{���R���e�i���Ɋ댯���ł��鎩�Ȕ����������Ȃ������Ȕ��M�����������[����Ă��邱�Ƃ�F�����邱�Ƃ��ł����B���̗g���ɂ́A�^���l�́A��K���A�덐���y��IMDG�R�[�h�ɂ��A���̐ύڕ��@���m�F���A�M��������̊u���y�эb��ύڂ����{���邱�Ƃ��ł����̂ŁA�{�����͔̂������Ȃ������B
�Ȃ��A����15�N�ȑO�y�і{�����̌�ɓ��l�̎��̂��������Ă��Ȃ��̂́A�{���e�ݕ����댯���ł���Ƃ̐\��������A�M��������̊u���y�эb��ύڂ��s��ꂽ���ʂł���B
�I �퍐�ɏd�ߎ�������Ƃ����邱��
�i�A�j���ΐӔC�@�ɂ�����d��ȉߎ��ɂ��āA�ō��ُ��a32�N7��9����O���@�씻���E���W11��7��1203�ł́A�u�����ɂ����d��ȉߎ��Ƃ́A�ʏ�l�ɗv���������x�̑����Ȓ��ӂ����Ȃ��ł��A�킸���̒��ӂ�������A���₷����@�L�Q�Ȍ��ʂ�\�����邱�Ƃ��ł����ꍇ�ł���̂ɁA���R����������������悤�ȁA�قƂ�nj̈ӂɋ߂����������ӌ��@�̏�Ԃ��w���v�Ɣ������Ă���B
�������Ȃ���A�����R�ٔ���ł́A�`���I�ɂ́u�̈ӂɋ߂����������ӌ��@�v�Ƃ����g�g��p���Ȃ�����A��̓I�Ȕ��f�ɍۂ��̈ӂƂ̑Δ�����݂ďd��ȉߎ��̗L���f�������̂͏��Ȃ��A�ނ���A�s�`�����̂����߂��Ă���ꍇ�A�Ƃ�킯�A�Ɩ���̒��Ӌ`���ᔽ������ꍇ�ɁA���̈ᔽ�������ďd�ߎ��Ɣ��f����X���ɂ���B�L�͂Ȋw�������̂悤�ȗ�����x�����Ă���B�d�ߎ����m�肵�������R�����́A�u�킸���̒��ӂŔF���������v�Ƃ��A���q�ϓI�Ɂu���������Ӌ`���ᔽ�v���̕\����p����̂���ʂł���B
�i�C�j�퍐�́A�ב��l�ł���ȏ�A����̐ӔC�ɂ����āA�C��^���Ɋւ���K�����m�F���A���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�댯���̉ב��l�ɉۂ���ꂽ�@�ߏ�̋`���́A�C��^�����̎��̂�h�~���邽�߂̂��̂ł���A�댯���̉ב��l�ɂ͍��x�̒��Ӌ`�����ۂ����Ă���Ƃ����ׂ��ł���B�댯���̊C��^���Ɋւ��A�ב��l�ɉۂ���ꂽ�e��̋`����S���m�F�����A���A���s���Ă��Ȃ����Ǝ��̂��A�댯������舵���A�C��^�����ϑ�����ב��l�ɗv������鍂�x�̒��Ӌ`�������ӂ������̂ł���A���������Ӌ`���ᔽ������B�퍐�ɂ͏d�ߎ�������Ƃ����ׂ��ł���B
�i�퍐�̎咣�j
�A �{���e�ݕ��́A���������K���y�ъ덐���ɂ�����댯���ɓ�����Ȃ��B
�{���e�ݕ����댯���ɊY�����邱�Ƃ�O��Ƃ��錴����̎咣�́A���ׂĎ����ł���B
�C ���ɖ{���e�ݕ����댯���ɊY������Ƃ��Ă��A��K���y�ъ덐���͎���@�K�ł���A����Ɉᔽ��������Ƃ����Ē����Ɏ��@��ߎ�������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�E �퍐�ɗ\���\�����Ȃ���������
�{���ł́A���̂Ƃ���A���ʉ���`���ᔽ�̑O��ƂȂ�\���\���������Ă�������A�퍐�����ʉ���`�����Ă����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�A�j�퍐�́A�{�����̂Ɏ���܂łɁA30��ȏ�A�{���e�ݕ��̊C��^�����ϑ����Ă���iPSR�[80�ɂ��ẮA����14�N2���ȍ~24��j�A1�x�����̂͂Ȃ������B�Ȃ��A����16�N5���ɓ��{���{��PSR-80�Ɠ���̉��w���Ƃ����CAS�ԍ�68584�[99�[6�̕��������A�ԍ�3228�̊댯�����Ɏw��\�����Ă����Ƃ��Ă��A����́A�⏕�Q���l�_�C�g�ꂩ��̏��ɂ����̂ł͂Ȃ��A�퍐�����{���{�Ɠ��l�̔F����L���Ă����킯�ł͂Ȃ��B
�i�C�j�{�����̂̌����͑D���̍�����3�R�����^���N�����̉��M�A�둀��ƁA�{���R���e�i���̃t�F���g�y���̑��݂ł���A��������퍐�ɂƂ��ė\���s�\�ł������B����ɁA�{�����Q������������Ȍ����͕s�K�Ȗ{�����������ɂ����̂ł���A������퍐�ɂƂ��ė\���s�\�ł������B
�i�E�j������́A�퍐���A�⏕�Q���l�_�C�g�[�ɖ{���e�ݕ��̊댯���]���������s�������ۂ����m�F���A�s���Ă��Ȃ��g���ɂ͕⏕�Q���l�_�C�g�[���͔퍐���炪�����@�ւɊ댯���]�������̎��{���˗����ׂ��ł������Ǝ咣����B
�������A�퍐�͏��Ђł���A�����ݔ���L���Ă��Ȃ����A�⏕�Q���l�_�C�g�[�����̂����{���e�ݕ���MSDS�ɊC��^���Ɋւ��댯���ł���|�̋L�ڂ͂���Ă��炸�A�댯���ł͂Ȃ����Ƌ^���ׂ����R�͂Ȃ������B���̓_�APSR�[80��MSDS�Ɂu�C�A�Ռ��A���C�A���̑��̔M���ɂ��A�e�Ղɕ����E�������鋰�ꂪ����B�v�Ƃ̋L�ڂ͂��������A���Ɂu130�x�i����_�j�v�Ƃ̋L�ڂ����邽�߁A�ێ�130�x����ꍇ�Ɍ����āA���ȕ������͔������̊댯��������̂Ɨ����ł���̂ł����āA�퍐�ɂ�����PSR-80���댯���ł͂Ȃ����Ƌ^���ׂ����R�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B
�܂��A��K���y�ъ덐���ɂ́A�ב��l�Ɋ댯���Y�����̔��f�`���A�����`���A���S�m�F�`���y�ѕ]���������s���`���킹��K��͂Ȃ��A�ݕ��̐�����ł��悭�m��⏕�Q���l�_�C�g�[��MSDS�ɂ����Ċ댯���ł���ƋL�ڂ���Ă��Ȃ������̂ł��邩��A����ȏ�ɔ퍐�ɂ����ĉ��炩�̒�����������`��������Ƃ͂����Ȃ��B
�i�G�j���ȉ����������x���ێ�55�x�ȉ��̊댯���ɂ��āA���x�Ǘ����v������Ă��邱�ƁiIMDG�R�[�h2.4.2.3.4.1�j���炷��ƁA�댯���̒ʏ�A�����ɓ��Ɏ��̂��z�肳���D�q���̉��x�́A�ێ�55�x���x�Ǝv����B�������A������āA�퍐���A�{���R���e�i���ɂ����āA10���ȏ�ێ�60�Ȃ���70�x���x�̍����������\����\���ł����Ƃ͂����Ȃ��i��29�j�B
�G �퍐�ɗ\���`���ᔽ���Ȃ�����
�퍐���A�����Ǝ҂ł���⏕�Q���l�_�C�g�[�ɑ��āA����I��MSDS�̋L�ړ��e�̕ύX�̗L�����m�F������A����I��MSDS�̌�t�����߂�ׂ��Ƃ����l�����́A����5�N3��26�������ȁE�ʏ��Y�Əȍ�����1���i��60�j���̋K���̊�{�I�ȍl�����ƍ��v���Ȃ��B
�I �퍐�Ɍ��ʉ���\�����Ȃ���������
���ɔ퍐�̗\���\�����m�肳���Ƃ��Ă��A�{���e�ݕ��̐ϕt���ʒu���w�������͕̂⏕�Q���l�_�C�g�[�ł���A�{���e�ݕ��̐ϕt�������{�����̂��퍐�ł͂Ȃ�����A�퍐�Ɍ��ʉ���\���͂Ȃ������B
�J �퍐�Ɍ��ʉ���`���ᔽ���Ȃ���������
�i�A�j�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�{�����̑O�ɖ{���e�ݕ��͂�������댯���ł͂Ȃ��Ƃ�������퍐�ɒ��Ă����B�{���e�ݕ��́A�{���R���e�i���{�D�ɑD�ς݂��ꂽ���_�ɂ����āA�댯���ɊY�����Ă��Ȃ������̂ł���A�퍐�͌����炪�咣����`�����Ă��Ȃ������B
�i�C�j�{���ł́A�퍐�͕⏕�Q���l�p���e�i��Ƃ̊Ԃʼn^���_���������A�⏕�Q���l�p���e�i�[�̓_���R�Ƃ̊Ԃʼn^���_���������A�_���R�̓s�[�E�A���h�E�I�[�Ƃ̊Ԃʼn^���_���������Ă����B
��������ƁA�퍐�́A�⏕�Q���l�p���e�i�[�Ƃ̊W�Ɍ����ĉב��l�ł���ɂ������A�_���R�y�уs�[�E�A���h�E�I�[�Ƃ̊W�ɂ����Ă͉ב��l�ł͂Ȃ��B
�i�E�j�댯�����ދ`���ɂ��āA������́A���ꂪIMDG�R�[�h�ɋK�肳��Ă���Ǝ咣���邪�A��L���_1�i�퍐�̎咣�j�A�̂Ƃ���AIMDG�R�[�h���̂��{���ɓK�p����鍪���͂Ȃ��B
���ɖ{���ɂ����Ċ댯�����ދ`�����F�߂���Ƃ��Ă��A�퍐�́A�����Ǝ҂ł���⏕�Q���l�_�C�g�[����MSDS���擾����Ȃǂ��āA���ЂƂ��Ĉ�ʓI�ɗv������钲�����s���AMSDS�̋L�ړ��e�ɏ]���Ă����̂ł��邩��A�댯�����ދ`�����ʂ����Ă����B������āA���Ђ̑��ŁA�����Ǝ҂̒�������e���^���A���玎�������{���A���͎����@�ւɈ˗����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����l�����́A�����ɂ����č̗p����Ă��Ȃ��B�����炪������x�m�ʐ^�t�C����������Ђ̗�́A�����I�ɂ͓��Ђ��������Ă���ƔF�߂����ł���A���Ђł���퍐�Ɠ���ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�G�j��ʓI���m�`���́A�댯���Ɍ����č��m�`�����ۂ���Ƃ�����K���̊�{�I�\���ɔ�������̂ł���A�F�߂��Ȃ��B
�i�I�j���m�O��`���́A�w����A�����Ǝ҂̋`���Ƃ��Ę_�����Ă���A���Ж��͉ב��l�̋`���Ƃ��Ă͘_�����Ă��Ȃ��B
�i�J�j������́A������3�̋`���ᔽ��_����ɓ�����A�ߎ����u�`���ᔽ�v�ɒu�������āA���́u�`���ᔽ�v������Δ퍐�͗L�ӂł���Ƃ����_�@���Ƃ��Ă���B�������A���̓��e�͂�������B���ł����āA�ߎ��ӔC�̌����ɔ����Ă���B
�L �d�ߎ��Ƃ͂����Ȃ�����
�{���ł́A�퍐�̉ߎ������F�߂��Ȃ��̂ł���A�d�ߎ����F�߂���]�n�͂Ȃ��B
���ɔ퍐�ɗ\���\���y�ь��ʉ���\�����F�߂��A�܂��A��K���y�ъ덐���Ɉᔽ�������Ƃ���퍐�ɒ��Ӌ`���ᔽ�����������Ƃ������㐄�肳���Ƃ��Ă��A���ΐӔC�@�̏d�ߎ��͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B�퍐�́A�⏕�Q���l�_�C�g�[����{���e�ݕ��͊댯���ł͂Ȃ��Ƃ̏����Ă���A�{���e�ݕ��̓��e�͂��̏��ɍ��v���Ă�������A�퍐���A�{���e�ݕ��͔�댯���ł���ƐM���������Ƃ͐����ł���B
�i5�j���_5�i���Q�̗L���y�ъz�j
�i������̎咣�j
�{���e�ݕ��́A���������K���y�ъ덐���̒�߂�댯���ł���B���̂��߁A�ב��l�ł���퍐�́A��K���y�ъ덐���ɒ�߂�ꂽ�e�[�u���Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɂ�������炸�A�����ӂ������߁A�{���R���e�i�́A�D�q���̍�����3�R�����^���N�t�߂ɐύڂ���A����ɂ��A���^���N�̉��M�Ɠ����ɔM�����A�{���R���e�i���̖{���e�ݕ������ȕ������N�����A�{�����U�����������B���̌��ʁA������́A���̂Ƃ���A���Q�����B�Ȃ��A��3���������ȊO�̌�����́A��ʓI�����Ƃ��āA�O���Ăɂ�鑹�Q�̔������A�\���I�����Ƃ��āA�~���Ăɂ�鑹�Q�̔����𐿋�����B
�i��1����������̎咣�j
�A �ݕ��ɌW�鑹�Q
�i�A�j���Q�̔���
�ʎ��u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v1�L�ڂ́u�ݕ��v���L�ڂ̊e�ݕ��ɂ��āA�{�����̖��͖{�����������ɂ��A���u��Q�ҁv���L�ڂ̊e��Q�҂ɓ��u���Q�z�v���L�ڂ̊e���Q�����������B
�i�C�j��ʓI�咣�|�ی���ʂɂ�鑹�Q�����������̎擾
�{�����̂ɐ旧���A��1����������́A��L�e�ݕ��ɂ��āA���ȒP�ƂŖ��͋����ی�����t���ŁA�ݕ��C��ی��_���������Ă����B�����ŁA��1����������́A��L�e�ی��_��Ɋ�Â��A��L�e�ݕ��ɐ��������Q�ɂ��āA���u�ی������v���L�ڂ̊����ɏ]���āA���u�ی����x���z�v���L�ڂ̂Ƃ���A��L�e��Q�҂ɑ��āA�ی������x�������i�x�������̈בփ��[�g�ɂ��~�����z�́A���ʎ��L��1�́u���{�~���Z�z�v���L�ڂ̂Ƃ���ł���B�j�B
����āA��1����������́A��������ی���ʂɊ�Â��A��L�e��Q�҂��L���Ă����퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q�������������擾�����B
�i�E�j�\���I�咣�|�����n�ɂ�鑹�Q�����������̎擾
���ɓ��ʎ�1�L�ځu�ݕ��ԍ��v1�Ȃ���7�A9�Ȃ���13�A15�Ȃ���24�A27�Ȃ���29�̊e�ݕ��ɂ��āA�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q��������������L�e��Q�҂ɋA�����Ȃ��Ƃ���A�����Q�����������͓��u�ב��l�v���L�ڂ̊e�ב��l�ɋA�����Ă����B
��1����������́A��L�e�ݕ��ɂ��āA�ʎ��u�����n�ژ^�i��1���������j�v�L�ڂ̂Ƃ���A��L�e�ב��l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q������������������B
�C �ٌ�m��p
�{�����Ă̓��ꐫ�A����A�i�ׂ̌o�ߓ��ɏƂ炵�A�{�����̂Ƒ������ʊW�̂���ٌ�m��p�́A��1����������e���ɂ��āA��L�A�i�A�j�̉��z��1��������Ȃ��B
�i��2����������y�ё�4����������̎咣�j
�A �ݕ��ɌW�鑹�Q
�i�A�j���Q�̔���
�ʎ��u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v2�y��3�L�ڂ́u�ݕ��v���L�ڂ̊e�ݕ��ɂ��āA�{�����̖��͖{�����������ɂ��A���u��Q�ҁv���L�ڂ̊e��Q�҂ɓ��u���Q�z�v���L�ڂ̊e���Q�����������B
�i�C�j��4���������[���b�N�X�̎咣
��4���������[���b�N�X�́A���ʎ�3�L�ځu�ݕ��ԍ��v10�ɌW��ב��l�̔퍐�ɑ���s�@�s�ׂɑ��鑹�Q������������������B
�i�E�j��2����������y�ь����[���b�N�X��������4����������̎�ʓI�咣�|�ی���ʂɂ�鑹�Q�����������̎擾
�����[���b�N�X��������2�����y�ё�4����������́A�{�����̂ɐ旧���A���ʎ�2�y��3�L�ځi���ʎ�3�L�ځu�ݕ��ԍ��v10�������B�ȉ������B�j�́u�ݕ��v���L�ڂ̊e�ݕ��ɂ��āA���u�ی������v���L�ڂ̂Ƃ���A�ݕ��C��ی��_���������Ă����B
�����ŁA�����[���b�N�X��������2�����y�ё�4����������́A��L�e�ی��_��Ɋ�Â��A��L�e�ו��ɐ��������Q�ɂ��āA���u�ی����x���z�v�L�ڂ̂Ƃ���A��L�e��Q�҂ɑ��āA�ی������x�������B
����āA�����[���b�N�X��������2�����y�ё�4����������́A��������ی���ʂɊ�Â��A��L�e��Q�҂��L���Ă����퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q�������������擾�����B
�i�G�j��2����������̗\���I�咣�[�����n�ɂ�鑹�Q�����������̎擾���ɓ��ʎ�2�L�ځu�ݕ��ԍ��v3�A4�A6�Ȃ���13�y��15�̊e�ݕ��ɂ��āA�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������������u��Q�ҁv���L�ڂ̊e��Q�҂ɋA�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����Q�����������͓��u�ב��l�v���L�ڂ̊e�ב��l�ɋA������B
��2����������́A�ʎ��u�����n�ژ^�i��2���������j�v�L�ڂ̂Ƃ���A��L�e�ב��l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������A��������A��L�e�ב��l��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
�i�I�j��4���������\���|�E�W���p���E���[���b�p�̗\���I�咣�[�����n�ɂ�鑹�Q�����������̎擾
a ���ɏ�L�i�E�l�̕ی���ʂɂ��퍐�ɑ��鑹�Q�����������̎擾���F�߂��Ȃ��Ƃ��Ă��A��4���������\���|�E�W���p���E���[���b�p�́A�ʎ��u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v3�L�ځu�ݕ��ԍ��v5�̉ݕ��ɂ��āA�ʎ��u�����n�ژ^�i��4���������j�v2�L�ڂ̂Ƃ���A��Q�҂ł����l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q����������������A����l��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
B ���ɕʎ�3�u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v�L�ځu�ݕ��ԍ��v5�̉ݕ��ɂ��āA�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q��������������l�ɋA�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����Q�����������͓��u�ב��l�v���L�ڂ̉ב��l�ɋA������B
��4���������\���|�E�W���p���E���[���b�p�́A���u�ݕ��ԍ��v5�̉ݕ��ɂ��āA�ʎ��u�����n�ژ^�i��4���������j�v1�L�ڂ̂Ƃ���A��L�ב��l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q����������������A���ב��l��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
�i�J�j��4���������A�N�T�A���}���n�C�}�[�A���N���o�O�[�A���Q�}�C�l�A���r�N�g���A�A���G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O�A���R���h�A�̗\���I�咣�[�����n�ɂ�鑹�Q�����������̎擾���ɏ�L�i�E�j�̕ی���ʂɂ��퍐�ɑ��鑹�Q�����������̎擾���F�߂��Ȃ��Ƃ��Ă��A��4���������A�N�T�A���}���n�C�}�[�A���N���o�O�[�A���Q�}�C�l�A���r�N�g���A�A���G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O�A���R���h�A�́A�ʎ��u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v3�L�ځu�ݕ��ԍ��v8�̉ݕ��ɂ��āA�ʎ��u�����n�ژ^�i��4���������j�v3�Ȃ���7�L�ڂ̂Ƃ���A��Q�҂ł����l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q����������������A����l��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
�i�L�j��4�����������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�̗\���I�咣�[�����n�ɂ�鑹�Q�����������̎擾
a ���ɏ�L�i�E�j�̕ی���ʂɂ��퍐�ɑ��鑹�Q�����������̎擾���F�߂��Ȃ��Ƃ��Ă��A��4�����������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�́A�ʎ��u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v3�L�ځu�ݕ��ԍ��v9�̉ݕ��ɂ����āA�ʎ��u�����n�ژ^�i��4���������j�v9�L�ڂ̂Ƃ���A��Q�҂ł����l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q����������������A����l��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
b ���ɕʎ�3�u�����瑹�Q�z�ꗗ�\�v�L�ځu�ݕ��ԍ��v9�̉ݕ��ɂ��āA�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q��������������l�ɋA�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����Q�����������͓��u�ב��l�v���L�ڂ̉ב��l�ɋA������B
��4�����������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�́A���u�ݕ��ԍ��v9�̉ݕ��ɂ��āA�ʎ��u�����n�ژ^�i��4���������j�v8�L�ڂ̂Ƃ���A��L�ב��l����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q����������������A���ב��l��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
�C �ٌ�m��p
�{�����Ă̓��ꐫ�A����A�i�ׂ̌o�ߓ��ɏƂ炵�A�{�����̂Ƒ������ʊW�̂���ٌ�m��p�́A��2�����y�ё�4����������e���ɂ��āA��L�A�i�A�j�̊e���z��1��������Ȃ��B
�i����NYK�̎咣�j
�A �{�����̂̌��ʁA��3�D�q���̖{���R���e�i���ςݕt�����Ă����ӏ��𒆐S�Ƃ��āA�{�D���ꕔ�đ��������Ƃ͂��Ƃ��A�{�����������A���������A�{�D�̉��C�U���̌��ʁA����NYK���{�D�̃T�[�x�C��p�A�{�����������ɗv������p�A���C�U��p�A�{�C�U��p�A�Ǘ���y�т��̑����o����x�o���A�܂��A�{�D�̉��C�U�y�і{�C�U�̊ԁA���邱�Ƃ̂ł����͂��̗��v���������̂́A�퍐���{���e�ݕ����댯���ł��邱�Ƃ̒ʍ���ӂ����Ƃ����s�@�s�ׂɂ���Ĕ����������Q�ł���B�퍐���A�{���e�ݕ��ɂ��Ċ댯���ʍ��̋`���𗚍s���Ă����Ȃ�A�{�D���ɂ����Ė{���R���e�i��M�����痣�ꂽ�b��̂ł��邾�����x�̒Ⴂ�g���ɐςݕt�����͂��ł���A�{�����̂�������邱�Ƃ��ł����B����āA�퍐�́A����NYK�ɑ��A�s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����ӔC���B
�C �܂��A���{�X�D�́A���L����R���e�i�i�R���e�i�ԍ�GATU1157375.20�t�B�[�g�E�h���C�R���e�i�j��{�D�ɐύڂ��Ă���A�{�����̂ɂ��A���R���e�i���đ������B���Y�đ��ɂ����{�X�D�̑��Q�́A1926.83�č��h���ł���B���{�X�D�́A��L���Q�ɂ��Ĕ퍐�ɑ��ĕs�@�s�ׂɊ�Â����Q������������L����Ƃ���A����17�N10��17���A��������������NYK�ɏ��n���A���̎|�퍐�ɑ����e�ؖ��X�ւɂĒʒm�����B
�E ����NYK�̖{�����̂ɂ�鑹�Q�z�́A5925��5008�~�A127��2001.30�č��h���i��L�C���܂ށB�j�i1�č��h��115.65�~���Z��1��4710��6950�~�j�A20��7428.11���[���i1���[��138.32�~���Z��2869��1456�~�j�A3��5570.21�|���h�i1�|���h202.44�~���Z��720��0833�~�j�A1��1389.06�V���K�|�[�ꃋ�h���i1�V���K�|�[���h��68.24619�~���Z��77��7260�~�j�A10���E�H���i1�E�H��0.1099�A3�~���Z��1��0993�~�j�̍��v2��4304��2500�~�ł���B
�܂��A�{�����Ă̓��ꐫ�A����A�i�ׂ̌o�ߓ��ɏƂ炵�A�{�����̂Ƒ������ʊW�̂���ٌ�m��p�́A��L���z�̂P���ł���2430��4250�~������Ȃ��B
�G ����āA���Q�z�́A2��6734��6750�~�ł���B
�i�������}�U�L�̎咣�j
�A �ݕ��̑��Q�ɂ���
�i�A�j��ʓI�咣
���}�U�L�}�U�b�N�g����f�B���O������Ёi�ȉ��u���}�U�L�}�U�b�N�g���[�f�B���O�v�Ƃ����B�j���ב��l�Ƃ��A�������}�U�L����l�Ƃ���������@�B�u�C���e�O���b�N�X300�[3ST�v�A�u�C���e�O���b�N�X300�\3�v�A�u�}���`�v���b�N�X6200�v�y�сuFMSFH1080�v�i�ȉ��u�{�������@�B�v�Ƒ��̂���B�j�́A����16�N9��29������A���É��`�ɂ����āA�{�D�̑�3�D�q���ɐύڂ���A��������邽�߁A���}�U�L�}�U�b�N�g���[�f�B���O�ɑ��āA�C��^����1�ʁi�^����ԍ�MISCNGOOOOOO2881�j�����s��t���ꂽ�B�{�������@�B�́A�{�����̂Ȃ������̏��̂��߂̊C���̕����ɂ�鐅�G��ɂ�葹�������B���̑��Q�z�́A82��8281���[���i1��3246��6980�~�j�ł���B
����āA�������}�U�L�́A�퍐�ɑ��āA���z�̕s�@�s�ׂɊ�Â����Q������������L����B
�i�C�j�\���I�咣
���ɖ{�������@�B�ɌW�鑹�Q�ɂ��Ă̔퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q�������������������}�U�L�ɋA�����Ȃ��g���ɂ́A�����Q�����������́A���}�U�L�}�U�b�N�g���[�f�B���O�ɋA�����邪�A�������}�U�L�́A���}�U�L�}�U�b�N�g���[�f�B���O����A�퍐�ɑ���s�@�s�ׂɊ�Â����Q����������������A���}�U�L�}�U�b�N�g���[�f�B���O��㗝���āA�퍐�ɑ��A��L�����n�̒ʒm�����A����20�N3��3���A���ꂪ�퍐�ɓ��B�����B
�C �ٌ�m��p
�{�����Ă̓��ꐫ�A����A�i�ׂ̌o�ߓ��ɏƂ炵�A�{�����̂Ƒ������ʊW�̂���ٌ�m��p�́A��L�A�̉��z��1��������Ȃ��B���̊z��1324��6698�~�ł���B
�E ����āA�������}�U�L�̑��Q�z�́A82��8281���[���y��1324��6698�~�ł���B
�i�퍐�̎咣�j
�A �{���e�ݕ��́A�댯���ł͂Ȃ��A�K���b��ɐύڂ��ꂽ�Ƃ͌���Ȃ��B���������āA���ɔ퍐�ɉߎ����͏d�ߎ�������Ƃ��Ă��A����Ƒ��Q�����Ƃ̊Ԃɑ������ʊW���Ȃ��B
�C �啔���̉ݕ��̑��Q�̌����́A�C�������ɂ��C���G��ɂ���B�����āA�X�v�����N���[�ɂ��C���U�z���������ƂŁA��3�D�q�̃n�b�`�R�[�~���O�i�D�q�̑q���̎��ӂɐ݂����鉏�ށj�̎��͂̉��x�͋}���ɉ����������ƁA�{�D�ɂ́A�\���Ȕr�o�\�͂̂���|���v���������Ă������Ƃ��炷��A�C�������͕s�v�ł������B����ɂ�������炸�A�C�����������ꂽ�̂́A��3�R�����^���N�����̉ߔM��Ԃ��p���邽�߂ł������ƍl����̂������I�ł���A���̂悤�ȉߔM��Ԃ������N�������ӔC�́A��猴��NYK�ɂ���B
�E ������̎咣��������n�ɂ��āA���̏���l�͑㗝�l�ɂ������n�_���������Ă��邪�A���̑㗝���̑��݂�����؋��͒�o����Ă��Ȃ�����A�����n�̎咣�͔ے肳���ׂ��ł���B
�i������̔��_�j
�A �{���R���e�i���b��ŁA���Ό��ƂȂ�ݔ��y�єM�����琅��������3m�ȏ㗣��A���A�ł�����艷�x�̒Ⴂ�g���ɐύڂ���Ă����Ƃ���Ζ{���e�ݕ��̔��Ɏ��邱�Ƃ͂Ȃ������B���ɁA�{���e�ݕ��������Ă����Ƃ��Ă��A�b��̐ϕt���ʒu�Ŕ����Ă����̂ł���A�����炪�ݕ��C��ی��������Ă����ݕ������[�����R���e�i�͑S�čb���ɐςݕt�����Ă����̂ł��邩��A���Q�͐����Ȃ������B�퍐���{���R���e�i�̊O�����ʂɊ�K���y�ъ덐���ŋ`���t�����Ă����W�D��t���邱�Ƃ�ӂ������ƁA�R���e�i�댯�������̒�o��ӂ������Ɠ��ƌ����炪�ݕ��C��ی��������Ă����ݕ������Q�������ƂƂ̊Ԃɂ͏����W������B
�C �����āA�������ʊW�́A�����ƌ��ʂƂ̊ԂɁA�i1�j�����W�����邩�A�i2�j�A�ӑ��������f�ɂ���āi1�j�ɂ��Ă̔��f���C������K�v�����邩�ۂ��ɂ���Ĕ��f�����Ƃ���A�{���ɂ����ẮA��L�A�̂Ƃ���A�{���e�ݕ��̊댯�������m���Ȃ������Ƃ����������Ȃ���Α��Q���������Ȃ������Ƃ��������W�����݂��A������C������A�ӑ��������f�v�f�͑��݂��Ȃ��B
�E �퍐�́A������3�R�����^���N���̔R�����ُ̈�ȉ��M���{�����̂̌����ł���Ǝ咣���邪�A�퍐�̖{���e�ݕ��̊댯���s���m���Ȃ���Ζ{���e�ݕ��́u�b��ύځv�i�덐���ʕ\��1���l7�j������Ă����͂��ł���A���ɁA������3�R�����^���N���̔R�����ُ̈���M���������Ƃ��Ă��A�b��ύڂ��ꂽ�{���e�ݕ��̔��Ό����ƂȂ�]�n�͂Ȃ��A�퍐�̎咣�́A���ʊW�̒��f���R�ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B
�G �܂��A�퍐�́A������̑��Q�͐��s�K�Ȓ��������ɂ����̂ł���Ǝ咣����B�������Ȃ���A�D���̓����\���͕��G�ŁA���C���\���ɂł��Ȃ��ꏊ�������A���̂悤�ȏꏊ�ɂ����鎖�̂ł���A�_����L�ŃK�X�ɂ��l�g���̂̊댯�����邵�A�D�̂̎�v�\���ޗ����|�ł��邱�Ƃ���A�M�`�������ǂ��A���ĉ\���������B����䂦�A�{�����̂̍ۂ��A���S�Ȓ������v�����ꂽ���A�����ŁA�{�����̓����A�D����́A���̌������g��������ł��Ă��Ȃ�������ɁA�D���̍\���̕��G������A��g�����Ώە��ڋ߂��Ē����������s�����Ƃ�����ł������B�܂��A�X�v�����N���[�ɂ��U���݂̂ł́A�R���e�i���̉ݕ��̏��m�F�ł����A���S�Ȓ�����}�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���̂悤�ȏɂ��݂�A�D�����A��_���Y�f�𓊓����A�X�v�����N���[�ɂ��U����������A�X�ɊC���𒍓��������Ƃ́A���S������ړI�Ƃ����K���Ȋ����Ƃ������Ƃ��ł���B
�i6�j���_�i6�j�i���v���E�|�����C�����S���������j
�i�퍐�̎咣�j
�{���ɂ��ẮA�����C���葱���i�s���ł���A������ɂ́A�{�i�ׂŐ������Ă��鑹�Q�̈ꕔ��U�₷�鋤���C�����S���������F�߂���\���������B�����C���葱���J�n����Ă�����ɂ����āA�d�˂ĕs�@�s�ׂɂ�鑹�Q���������i�ׂ��N���邱�Ƃ́A�ߏ�Ȍ����s�g�ł���A�����炪�����C�����S����������������Ȃ�����A�ے肳���ׂ��ł���B���������āA�{�i�ׂɂ����鐿���͑��₩�Ɋ��p�����ׂ��ł���B
�i������̎咣�j
�A �����C�����S�������Ɩ{�i�ɂ�鑹�Q�����������̂�������s�g���邩�́A������ɂ����ĔC�ӂɌ��߂邱�Ƃ��ł���B
�C �����C���葱�́A�L�ӂȎ҂�����ꍇ�ɂ͂��̎҂ɑ��鋁����\�肵�Ă���A�퍐�͗L�ӂȎ҂ł��邩��A���Ɍ�����ɋ����C�����S������������Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ𗝗R�ɔ퍐���s�@�s�אӔC��Ƃ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i7�j���_7�i���Ŏ����̐���1�j
�i�퍐�̎咣�j
�A ���������C������́A����19�N12��21���t���u�i���ύX�y�ёi������\�����v�ɂ����āA�]���̐����ɉ����āA�ʎ��u�����瑹�Q�z�ꗗ�v1�L�ځu�ݕ��ԍ��v29�Ɋւ��鐿�����z521��6664�~��lj������B
��L�ݕ��́A55����̐����p�����ԕ��i�ł���A�ی��҂����������C������A��ی��Ҍ����傪�~�c�r�V�E���[�^�[�Y�E���[���u�EB.V.�iMitsubishi Motors Europe B.V.�ȉ��u�~�c�r�V�E���[�^�[�Y�E���[���v�v�Ƃ����B�j�ł������B
�C �~�c�r�V�E���[�^�[�Y�E���[���u�́A�x���Ƃ�����16�N12��10���ɁA���Q�y�щ��Q�҂�m�����B
�E ����19�N12��10���͌o�߂����B
�G �퍐�́A����20�N2��12���̖{����8��٘_�����葱�����ɂ����āA��L���������p�����B
�i���������C������̎咣�j
�퍐�̎咣�A�͔F�߁A���C�͔۔F����B
�J�j���K���E�����[�C������Ёi�ȉ��u�J�j���K���E�����[�C�v�Ƃ����B�j�́A����16�N12��1���t���u��2���\�����v�i�b�C2�j���쐬�������A�����ɂ����Ė{�����̂̌����ɂ��čŏI�I�Ȍ��_�𗯕ۂ��A�������Ƃ��Ă����B�����āA�J�j���K���E�����[�C�́A����17�N3��9���t���ŏI���i�b�C3�y��4�B�ȉ��u�J�j���K���E���|�[�g�v�Ƃ����B�j�ɂ����āA����16�N12��21���̒������ʂ������܂��A���߂Ĕ퍐���{�����̂ɂ��ėL�ӂł���ƌ��_�t�����B���������āA���������C������́A����16�N12���̎��_�ł͉��Q�҂�m��Ȃ������B
�i8�l���_8�i���Ŏ����̐���2�j
�i�퍐�̎咣�j
�A �������}�U�L�́A����20�N2��4���A��5�����̑i�����N�����B
�C �������}�U�L�́A�x���Ƃ�����16�N12��31���܂łɑ��Q�y�щ��Q�҂�m�����B
�E ����19�N12��31���͌o�߂����B
�G �퍐�́A����20�N4��15���̖{����9��٘_�����葱�����ɂ����āA��L���������p�����B
�i�������}�U�L�̎咣�j
�퍐�̎咣�C�͔۔F����B
�������A�퍐���咣���鎞���Ɂu���Q�ҋy�ё��Q��m�����v���Ƃ������؋��͂Ȃ��A���̂悤�Ȏ����͔F�߂��Ȃ��B
��3�@���ٔ����̔��f
1�@�@���f�̍\��
�{���ɂ����铖�ٔ����̔��f�̍\���ɂ��Ă܂������Ă����B
�{���̑��_�́A�퍐�ɕs�@�s�אӔC�����邩�ۂ��i���_1�Ȃ���4�j�A�퍐�ɕs�@�s�אӔC������ꍇ�ɂ́A���̑��Q�̊z�i���_5�j�A����ɁA�R�قƂ��đ��v���E�[�����C�����S���������̗L���i���_6�j���͏��Ŏ����̐��ہi���_7�y��8�j�ł���B
�܂��A�O��ƂȂ鎖���W���m�肷�邽�߁A�{���e�ݕ����댯���ɊY�����邩�ۂ��i���_1�j�y�і{�����̂̌����i���_2�j�ɂ��Ĕ��f����i���_1�y�ё��_2�́A���_3�̔��f�̈ꕔ���\��������̂ł��邪�A���ɖ{���e�ݕ����댯���ł͂Ȃ��A�{�����̂̌����ł��Ȃ��Ƃ���A���_3�ȉ��̔��f�͕s�v�ƂȂ�B�j�B
���ɁA�{���e�ݕ��̑S�����͈ꕔ���A��K���y�ъ덐����A�댯���ł���A�{�����̂̌����ł���ƔF�肷�邱�Ƃ��ł���ꍇ�ɂ́A�퍐�̍s�ׂɂ��Ė@�I�]���������A���ΐӔC�@�̓K�p�̗L���i���_3�j�A�퍐�̗\���\���̗L���A���Ӌ`���̓��e�y�т��̜�ӂ̗L�����ɂ��Č������A�ߎ����͏d�ߎ������邩�ۂ��i���_4�j�ɂ��Ă̔��f������B
����ɁA���ɔ퍐�ɉߎ����͏d�ߎ����F�߂���ꍇ�ɂ́A���Q�̗L���y�ъz�i���_5�j���тɍR�فi���_6�Ȃ���8�j�ɂ��Ĕ��f���邱�ƂƂ���B
2�@�@���_1�i�{���e�ݕ��̊댯���Y�����j�ɂ���
�i1�j�댯���̈Ӌ`�ɂ���
�{�D�ɂ��Ă͓��{�D���ł͂Ȃ��Ă��D�����S�@�̋K�肪���p�����Ƃ���i���@29����7�j�A���@28��1���́A�댯���̉^���Ɋւ���Z�p�I������y��ʏȗ߂ɈϔC���Ă���i�Ȃ��A�D�����S�@�{�s��1���y��2���́A���@28�������p�����K��ɋ����Ă��Ȃ����A�����́A���̋K��̐��i���炵�āA�O���D���ɂ��ē��R�ɏ��p�������̂ł���Ɖ������B�j�B���ϔC������K��2��1���́A�댯���̒�`�K���u���Ă���A������Łu�R�������ށv���댯���̈�ł���Ƃ���A�R�������ނ́A�R�������i�C���ɂ��e�Ղɓ_����A���A�R�Ă��₷�������ŁA�����Œ�߂���̂������B������i1�j�j�A���R���ΐ������i���R���M���͎��R�����₷�������ŁA�����Œ�߂���̂������B������i2�j�j�y�ѐ������R�������i���ƍ�p���Ĉ��ΐ��K�X�����镨���ŁA�����Œ�߂���̂������B������i3�j�j��3�̂��̂Ƃ���Ă���B�����āA�덐��2��4���́A��K��2��1����i1�j�A�i2�j�y�сi3�j�̍����Œ�߂���̂��u���ꂼ��A�ʕ\���̕i���̗��Ɍf���镨���̂����A���ڂ̗����R�������A���R���ΐ������y�ѐ������R�������ł�����́v�Ƃ��Ă���B
�덐���ʕ\��1�̕i�����́u���Ȕ���������D�i�ő́j�i���l1�i2�j�̕\�Ɍf����ꂽ���́j�v�i���A�ԍ�3226�j�́A���ڂ̗����R�������ł���A���i�����́u���Ȕ��M�������i�L�@���j�i�ő́j�i���ɕi������������Ă�����̂������B�j�v�i���A�ԍ�3088�j�́A���ڂ̗������R���ΐ������ł��邩��A�����́A���������K��2��1���ɋK�肷��댯���ł���B
�i2�jNA�[125�̊댯���Y����
�A NA�[125�̉R�������Y����
�i�A�j�؋��i�b�C137��1�A�b��6�A7�A44�A��1�A4�A29�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���̎������F�߂���
�덐���ʕ\��1���l1�i2�j�̕\�́A���w���u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�����A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�́j�ɕ��ނ��Ă��邪�A���\�̎��Ȕ���������D�i�ő́j���ɉ��w���u2�[�W�A�]�[1��i�t�g�[���[5��X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�͑����Ȃ��B
���\�̎��Ȕ���������D�i�ő́j���ɂ́A�u���̑��̉��w���v�̂��̂��L�ڂ���Ă���Ƃ���A�u���̑��̉��w���v�̔���́A�����́AIMDG�R�[�h�ɋK�肷��L�@�ߎ_�����̊댯���敪�̂��߂̎������@�y�ѕi���̔�����@�̂����A�D�Вn���NJ�����n���^�A�ǒ����K���ƔF�߂���̂ɂ�蔻�肷��Ƃ���Ă����i�덐���ʕ\��1���l1�i2�j�̕\�̔��l1�j�B�Ȃ��A���݂̊덐���ɂ����ẮA�u���̑��̉��w���v�̃^�C�v�́A�덐���ʕ\��1���l2�i5�l�iii�j�̔����ɂ�茈�肷����̂Ƃ���Ă���i�����l1�i2�j�̕\��1�j�B�����l2�i5�j�iii�j�ɂ��A���Ȕ����������̃^�C�v�̔����͓����l2�i5�j�iii�j�̕\�̂Ƃ���ł���A�����IMDG�R�[�h2.4.2.3.3�ɋK�肷�鎩�Ȕ����������̎����ɂ����̂Ƃ���A�X�ɁA���̂����ꂩ�ɊY��������̂́A���Ȕ����������ɂ͊Y�����Ȃ��Ƃ����i���\�̒�1�y��2�j
�i1�j���
�i2�j�_���������i�R���̗L�@����5����%�ȏ�܂ނ��̂������B�j
�i3�j�L�@�ߎ_����
�i4�j50Kg��e��Ɏ��[������Ԃ̎��ȉ����������x���ێ�75�x���镨��
�i5�j����M��300J/g�����̂���
���y��ʏȊC���nj������x�ے��ʒB�u�����̊댯���]���̎������@�y�є����v�i���C����263����3�B����14�N8��21���t���j�́A���Ȕ����������ɂ��A�u�M�I�ɕs����ȕ����ł���A�_�f�i��C�j�̋������Ȃ��ꍇ�ł����Ă�����Ɏ��ȕ������Ղ������v�Ƃ�����A50Kg�̗A�����ɂ����鎩�ȉ����������x���ێ�75�x������͎̂��Ȕ����������ɊY�����Ȃ����̂ƒ�߂Ă���i��6�߂�1�A2.1�j�B
�����̌��ʁANA�[125�́A���̔Z�x�i���x�j���ő�92.1%�ł���A7.9%�ȏ�̕s�����y�ѐ������܂܂�Ă���A50Kg�̗A�����ɂ����鎩�ȉ����������x�́A�ێ�75�x���Ă�����̂ł������B
�i�C�j�ȏ�ɂ��A�܂��ANA�[125�́A�u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�|�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�ɂ͊Y�����Ȃ��B���̓_�ɂ��āA������́ANA-125�ɐ�߂�댯���̔Z�x��90%���A��%���x�̐������܂ނ���Ƃ����Ċ댯�����������ꂽ�Ƃ͂����Ȃ�����A�H�ƓI���i�͔Z�x��100����%�̂��̂ɓ�����Ǝ咣���邪�A7.9%�ȏ�̕s�����y�ѐ������܂܂�Ă���NA�[125���H�ƓI���i�Ƃ������Ƃ��ł��邩�ǂ����͋^�₪����A�܂��A��%�̐����y�ѕs�������܂ޕ����ɂ��Ă��u�Z�x��100����%�̂��́v�Ƃ������Ƃ��ł��邱�Ƃ�F�߂�ɑ����؋����Ȃ��B������̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�E�j�����A�덐���ʕ\��1���l1�i2�j�̕\�ɂ́A�u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�Ƃ������w���͑����Ȃ����A���̂悤�ȕ��������悻�댯����L���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ł����A�����l1�i2�j�̕\�Ɠ����e�ł���IMDG�R�[�h�́A�Z�p�I�ɏ����ȕ����łȂ����̂Ɋւ��ẮAIMDG�R�[�h�̎葱�ɏ]���ĈقȂ��ĕ��ނ��꓾��Ƃ��Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�i�g���E���i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�́A���̊댯���ɉ����āu���̑��̉��w���v�Ƃ��āA���Ȕ���������D�i�ő́j�ɕ��ނ����\�������蓾��Ƃ����ׂ��ł���B
�������Ȃ���ANA�[125�́A��L�i�A�j�̂Ƃ���A50Kg�̗A�����ɂ����鎩�ȉ����������x���ێ�75�x����̂ł���A���Ȕ������������珜�O����鐫����L���Ă��邩��A���A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�́j�̂����u���̑��̉��w���v�ɊY�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�C NA�[125�̎��Ȕ��ΐ������Y����
�i�A�j�؋��i�b�C137��1�A�b��6�A����17�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���̎������F�߂���B
�덐���ʕ\��1�́A�u���Ȕ��M�������i�L�@���j�i�ő́j�i���ɕi������������Ă�����̂������B�j�v�i���A�ԍ�3088�j�́A�R�������ނ̂������R���ΐ������ɊY�����A���̓�����4.2�A�e�퓙���͇U���͇V�Ƃ��Ă���B
���ʕ\��1���l2�i3�j�́A�R�������ނɂ��āA����̕i���ɑ��āA�����̗e�퓙�����f�����Ă���ꍇ�ɂ́A�R�đ��x�����A���R���ΐ��������͐��Ƃ̔������������{���A���̎������тɊ�Â����肷��Ƃ��Ă���B
�R�������ނ́A�R�������A���R���ΐ������i�L�`�j�y�ѐ��������R�������ɕ��ނ���A�L�`�̎��R���ΐ������Ƃ́A���R���M���͎��R�����₷�������������A���`�̎��R���ΐ������Ǝ��Ȕ��M�������ɕ��ނ���A���`�̎��R���ΐ������Ƃ́A���ʂł����Ă���C�Ɛڂ���5���ȓ��ɔ����镨���������A���Ȕ��M�������Ƃ́A���`�̎��R���ΐ������ȊO�̕����ł����āA��C�Ɛڂ����ꍇ�ɃG�l���M�[�̋����Ȃ��Ɏ��R�����₷�������ŁA��ʁi��Kg�j�������ԁi�����Ԗ��͐����j�o�߂����g���Ɍ��蔭���₷�����̂������Ƃ���Ă���B�J���e�b�N���s����NA�\125�ɑ���u�댯���A���Ɋւ��鍑�A�����̎����y�щ��w�����̊댯���]�������v�ɂ����āA����17�N12��9�����{�̎��Ȕ��M�������̌��ʂ́A�uClass4.2���Ȕ��M�������ɊY������B�e�퓙���U�v�Ƃ̔���ł������B�����A����8�����{�̎��R���ΐ������ɂ����ẮANA-125�́A�uClass4.2���R���ΐ������ɊY�����Ȃ��B�v�Ƃ̔���ł������B���̂����ANA�[125�����Ȕ��M�������ɊY������Ƃ����������ʁi����17�j�́A���̎������@�����A�����ɉ������̂ł����āA�M�p�̂ł�����̂ł���B
�i�C�j�ȏォ�炷��ƁANA-125�́A���Ȕ��M�������i�L�@���j�i�ő́j�i���A�ԍ�3088�j�ɊY��������̂ł���A���̊덐���ʕ\��1�̍��ڂ̗��͎��R���ΐ������ł��邩��A�댯���ł���R�������ނɊY������Ƃ������Ƃ��ł���B
�E ����
�ȏ�ɂ��ANA�[125�́A��K��2��1���ɋK�肷��댯���ɊY������B
�i3�jPSR�[80�̊댯���Y����
�A PSR�[80�̉R�������Y����
�i�A�j�؋��i�b�n8�A33�A��16�A17�A����3�Ȃ���5�A15�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���̎������F�߂���B
�덐���ʕ\��1���l1�i2�j�̕\�́A���w���u2�[�W�A�]�[1�[�i�t�g�j���[5�[�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�y�сu2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[�X���z���_�G�X�e��D�i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�����A�ԍ�3226:���Ȕ���������D�i�́j�ɕ��ނ��Ă���B
PSR-80�́A1.0�Ȃ���1.2%�̐������܂݁A���v3.0%�ȉ��̕s�������܂�ł�����̂ł������B�⏕�Q���l�_�C�g�[���APSR�[80�ɂ��āA�J���e�b�N�y�ѓ��{�C�����苦����w���̓Z���^�[�Ɉ˗����Ė{�����̌�ɒ~�M�����������n�߂Ƃ���N���X4�̊댯���Y�����̔��莎�����s�������ʁAPSR�[80�́A50Kg�̗A�����ɂ����鎩�ȉ����������x���ێ�70�x�ƁA���肳��A�R�đ��x��������N���X4.1�̉R�������ށE�R�������i�e�퓙���V�j�ɊY������Ɣ��肳�ꂽ�B
�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�{�����̌�APSR�[80�ɂ����āA���A�ԍ�3226�y��3228�̊댯���ɊY��������̂Ƃ��Ď�舵�����ƂƂ����B
�i�C�j�ȏ�ɂ��APSR-80�́A�Z�x��100����%�̂��̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł����A���w���u2�|�W�A�]�[1�[�i�t�g�[���[5�[�X���z���_�G�X�e���i�Z�x��100����%�̂��́j�v�ɂ͊Y�������A�܂��A���Ȕ���������D�̗v���ɓK�����邩�ۂ��̔���͂���Ă��Ȃ�����A�u2�[�W�A�]�[1�|�i�t�g�[���[�X���z���_�G�X�e��D�i�Z�x��100����%�����̂��́j�v�ɊY�����邱�Ƃ�F�߂�ɑ����؋����Ȃ��B
�������Ȃ���A��L�i�A�j�̂Ƃ���A�����̌��ʁAPSR-80�́A�N���X4.1�̉R�������ށE�R�������i�e�퓙��III�j�ɊY������Ɣ��肳��Ă���A���̌�̕⏕�Q���l�_�C�g�[��PSR-80�̎戵���ɂ��݂�ƁA�u���̑��̉��w���v�Ƃ��āA�R�������ł��鍑�A�ԍ�3226�F���Ȕ���������D�i�́j���͍��A�ԍ�3228:���Ȕ���������E�i�ő́j�ɊY������Ƃ������Ƃ��ł���B
�C PSR�[80�̎��R���ΐ������Y����
�i�A�j�؋��i����16�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���{�C�����苦����w���̓Z���^�[��PSR-80�ɑ��镽��16�N12��24�����{�̎��R���ΐ������y�ю��Ȕ��M�������̌��ʂ́A�O�҂��u�R�������ށA���R���ΐ������A�e�퓙���T�ɊY�����Ȃ��B�v�A��҂��u���Ȕ��M�������A�e�퓙���U�ɊY������B�v�Ƃ̔���ł��������Ƃ��F�߂���BPSR-80�����Ȕ��M�������ɊY������Ƃ������������ʂ́A���̎������@�����A�����ɉ������̂ł����āA�M�p�̂ł�����̂ł���B
�i�C�j�ȏォ�炷��ƁAPSR�[80�́A���Ȕ��M�������i�L�@���j�i�ő́j�i���A�ԍ�3088�j�ɊY��������̂ł���A�덐���ʕ\��1�̍��ڂ̗������R���ΐ������ł��邩��A�댯���ł���R�������ނɊY������Ƃ������Ƃ��ł���B
�E ����
����āAPSR-80�́A�R�������ނ̂����R�������y�ю��R���ΐ������ɊY��������̂ł����āA��K��2��1���ɋK�肷��댯���ɊY������B
3�@���_2�i�{�����̂̌����j�ɂ���
�i1�j�؋��i��Ɍf�������́j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���̎������F�߂���B
�A �{�����̂̔����Ɏ���܂ł̏i�b�n22�A��7��1�A2�A��8�A9�A11�Ȃ���13�A16�A21�A22�A24�A25�j
�i�A�j�퍐�́A����15�N12��16���A�f�B�[�P�C�G�X�G�C�`�E�X�E�B�b�@�[�����h�E���~�e�b�h�iDKSH Switzerland Ltd.�ȉ��uDKSH�v�Ƃ����B�j�ɑ��āANA�|125���v3��Kg�i6�P�ʁB1�P��5000Kg�j���A������v4620���~�i1�P�ʊe770���~�j�Ŕ������B
DKSH�́A����16�N8��16���A�퍐�ɑ��ANA-125�i500oKg�j�̓��{�����6��ڂ̑D�ς݂��w�����A�퍐�́A����19���A��L�w�����m�F�����B
DKSH�́A���N9��8���A�퍐�ɑ���PSR-80�i400Kg�j�̏o�ׂ��w�����A�퍐�́A����9���A��L�w�����m�F���ADKSH�ɑ��āAPSR-80�i400Kg�j����792��2000�~�Ŕ������B
�i�C�j�퍐�́A���N8��17���A�⏕�Q���l�_�C�g�[�ɑ���50OOKg��NA�[125�̍w����\�����݁A�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�������785��9250�~�Ŕ���A�t�@�C�o�[�h������10O�ɍ���āA�쐼�q�ɐ_�ˎx�X�Z�b�^�[�~�i�����c�Ə��i�_�ˎs�������m����1-1���݁j�ň����n�����Ƃ���B
�퍐�́A���N9��9������A�⏕�Q���l�_�C�g�[�ɑ���400Kg��PSR�[80�̍w����\�����݁A�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A����13������A�������735���~�Ŕ���A�J�[�g��10�ɍ���āA��L�c�Ə��ň����n�����Ƃ���B
�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A����22����PSR-80���A����24����NA-125�����ꂼ��퍐�Ɉ����n�����B
�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�퍐�ɑ��āANA-125�ɂ��A���N9��10���t���u���͏ؖ����v�i��1�j���APSR-80�ɂ��A����15���t���u���͏ؖ����v�i��16�j���A���ꂼ���t�����BPSR�[80�̕��͏ؖ����ɂ́A�u�ۊǁv���Ɂu�Ռ����A��������߂��e��ŗ�Ï��ɕۊǁv�ƋL�ڂ���Ă����B
�i�E�j�퍐�́A���N9��22���t�������ŁADKSH�ɑ��A5000Kg��NA-125�i���770���~�B�t�@�C�o�[�h�����ʁi����́A�������t�@�C�o�[�h���������A�ꕔ���|�[�����y�э����łł������̂ł����āA�S���̊W�y�ђ��߃o���h���t���Ă�����̂ł���B�j100���j�y��400Kg��PSR�[80�i���729��200O�~�B�J�[�g���i����́A�i�{�[�����ł���B�j40���j���A����28���ɐ_�˂��o�q���A���b�e���_���܂ŁA�{�D�ʼn^�����邱�Ɠ���ʒm���i��14�j�A����24���A�{���e�ݕ��ɂ��Ĉ��n�m�F���i��15�A26�j�𑗕t�����B
�i�G�j�{���e�ݕ��́A���N9��27������A�_�ˍ`�̃R���e�i�E�t���C�g�X�e�[�V�����ɂ����Ė{���R���e�i�Ɏ��[����A�{���R���e�i�́A�{�D�ɐςݕt����ꂽ�B
�{�D�́A����28���ɐ_�ˍ`���A���N10��1���ɐ����`���A����8���ɃV���K�|�[���`���A���ꂼ��o�`�����B�V���K�|�[���o�`���̖{�D�̏�Ԃ́A���̂Ƃ���ł������B
a �ύڃR���e�i�� 3559��
b �ύڊ댯���R���e�i�� 80��
c �ύڗⓀ�R���e�i�� 92��
d �R��
�E����3�R�����^���N ��500�g��
������3�R�����^���N ��500�g��
�E����4�R�����^���N ��900�g��
������4�R�����^���N ��903�g��
�E����7�R�����^���N ��1000�g��
������7�R�����^���N ��1000�g��
���̑� ��180�g��
e �f�B�[�[���� ��213�g��
�i�I�j�����H6�N10��13���ߑO11��30�����_�ő�3�R�����^���N���̔R�����́A������446.1�g���Ai�ێ�32�x�A�E����444.6�g���A�ێ�37�x�ł����āA���Ɉُ�͂Ȃ������B
�{�D�́A����16���ߌ�9��30���A�X�G�Y�`�ɓ��`���A����17���ߌ�5���A�X�G�Y�^�͂�ʍq���āA�|�[�g�E�T�C�h��ʉ߂����B���̂��덶�E�̑�3�R�����^���N�̉��M���J�n���ꂽ�B����18���ߌ�10�����납��A�E����3�R�����^���N�̔R��������R���Ƃ��ėp�����n�߂��B���̂Ƃ����E�e���̔R�����̉��x�́A�ێ�30�x�ł������B
�i�J�j����19���ߑO7��30���A������3�R�����^���N�̔R�����i452.0�g���j�Ɏ�R������ւ���ꂽ�B���̂Ƃ��A�E���̎c�R�����́A428.7�g���A���x�͐ێ�33�x�ł������B�����ߌ�5��30���A�E����3�R�����^���N�̔R�����Ɏ�R������ւ���ꂽ�B
�C �{�����̔������̏i�b�n10�Y�t�̍q�C���������A�b�n20�A22�Ȃ���32�j
�i�A�j����19���ߌ�11��55���A�{�D���k��38�x�A���o6�x39��3�b���q�C���A�{�D�̉����m���u����3�D�q�ɂ�����Ђ�m�点��x�����B
�j�R���E�^�o�[���D���i�ȉ��u�D���v�Ƃ����B�j�́A�����ߌ�11��58���A�A���o�g���j���q�C�m�i�ȉ��u�q�C�m�v�Ƃ����B�j�ɑ��A��3�D�q�ɍs���A�����ĕ���悤�ɖ������B
�i�C�j����20���ߑO0��00������A�D�̂̑O�������ʂ̉����o���B
�q�C�m�́A��3�D�q�̃}���z�[�����牌���o�Ă��邱�Ƃ��m�F���A�D���ɕ����B
�D���́A�q�C�m�ɑ��A���̃}���z�[�������āA�����ɋ��Z��Ɉ����Ԃ��悤�������B
�D���́A���x���炵�A�D�������ʼnЂ̎����\�������B
�i�E�j�����ߑO0��13���A��4�D�q�̉����m���u���x�����B
�D���́A�����ߑO0��24���A�q�C�m�ɑ��A��3�D�q�̂��ׂĂ̒ʕ����Ւf���邱�Ƃ̊m�F�𖽂���ƂƂ��ɁA�ʕ��Ւf���m�F���Ă�������ǂ������S�������Z��ɖ߂����B�����ߑO0��20������ߑO0��30���܂ł̖�A��3�R�����^���N�������u���m�@�ǎ�l�̉��x�͐ێ�92�x�i���[�l��0.25m�j�������Ă����B
�i�G�j�D���́A�����ߑO1��45���܂łɑ�1�Ȃ�����4�D�q�̒ʕ����u���Ւf���A��3�D�q�ɒY�_�K�X�𒍓�����ƂƂ��ɁA��3�D�q�b��őD�q�̋��E�����p����ȂǑ�3�D�q����̉��Ă�}���鏉���������������A�����ߑO1��46���A�D���Ǘ��l�ł���V���K�|�[���̃G�k���C�P�[�E�V�b�v�}�l�W�����g�E�s�[�e�B�[�C�[�E���~�e�b�h�iNYK Shipmanagement Pte. Ltd. �ȉ��u�D���Ǘ��l�v�Ƃ����B�j�y�эЊQ�����Z���^�[�ɓd�b�Ŏ��̏�`�B�����B�Ȃ��A��3�����R�����^���N�̉��x�Z���T�[�́A�����ߑO2������ߑO3��30������܂ŁA�ێ�92�x�i���[�v0.25m�j���������܂܂ł������B����A�E���R�����^���N�̕\���v�́A�ێ�55�x�ł������B
�D���́A�q�C�m�ɑ��A������3�R�����^���N�̔R�������ێ�92�x�ɒB���Ă������ȏL���Ə��C����C��������o�Ă���͂��ł���Ƃ��āA��b�̋�C��������̏L���̗L�����`�F�b�N����悤�ɖ������B�q�C�m�́A�����ߑO3��20������A�����A�E���A������̔R�����^���N�̋�C����������R�����̏L�����Ȃ��|��D���ɕ����B
�i�I�j�ꓙ�q�C�m�́A�����ߑO3��20���A��3�D�q�b�̃R�[�~���O�y�эb���ʘH�u�ǂ̉��x�𑪒肵���Ƃ���A�ێ�30�Ȃ���40�x�ł������B
�D���́A�����ߑO3��33���A�D���Ǘ��l�ɑ��A�d�b�ŁA���Ό�����肵�Ă��Ȃ����ƁA�Ĕ��̊댯�����邱�ƁA�Y�_�K�X�̒���p���p�������邱�Ƃ�����ł��铙�Ƃ��āA�U�����K�v�ł���Ƃ̍l�����������B�Ȃ��A�����ߑO3��37���ɂ�����x�C22�����t�߂̍������̉��x�͐ێ�56�x�A�x�C22�Ȃ���26�̑D�������ʘH�b�̉��x�͐ێ�69�x�ł������B
�i�J�j�D���Ǘ����́A�����ߑO3��50���A�D���ɑ��A�X�v�����N���[�z�njn�̎g�p�������A�X�v�����N���[�z�njn�̌��ʂ傳���邽�߁A�Y�_�K�X�n�ɏ��Ηp�̊C����ڑ����ׂ��ł���Ƃ��A������đD���́A�ߑO3��55���A�ꓙ�q�C�m�ɑ��A�n�b�`�J�o�[�̃X�v�����N���[�z�njn�ɊC����ڑ�����悤�w�������B�����ߑO4���A�X�v�����N���[�z�njn���쓮���A�C���̒������J�n���ꂽ�B
�D���́A�����ߑO4��15���A�������Ȃ��Ȃ����Ƃ̕��đ�3�D�q�̉��T�m�@�����Z�b�g�����Ƃ���A�ēx�x�u���쓮�����B
�����ŁA�D���́A�����ߑO4��30���A�@�֒��ɑ��A��3�D�q�̒Y�_�K�X�z�njn�ɏ��Ηp����ʂ��悤�w�������B
�q�C�m�͑�3�n�b�`�J�o�[����Z���������邱�Ƃ��A�ꓙ�q�C�m�͑�3�D�q�E���u�ǂ̉��x���ێ�42�x�ł���A�㕔�E���u�ǂ̉��x���ێ�46�x�ł��邱�ƁA�D���ʘH�b�̉��x���ێ�50�x�ł��邱�Ƃ��A���ꂼ��m�F�����B
�ꓙ�q�C�m���A�����ߑO5���A�q�C�m�y�уC�r�J�E�|�|�r�c�N�[���@�֎m�i�ȉ��u�ꓙ�@�֎m�v�Ƃ����B�j�Ƌ��ɍ�����3�R�����^���N���㕔�̉��x��_�������Ƃ���A�ێ�70�x�ł������B�����ߑO5��15������A�ꓙ�@�֎m�炪���E��3�R�����^���N�̑��[�l��_������ƁA������3�R�����^���N�̑��[�l�́A3.10m�A�E����3�R�����^���N�̑��[�l��2.48m�ł������B
�i�L�j�D���Ǘ��l�́A�����ߑO6�����O�ɁA�D���ɑ��A�Y�_�K�X�̎g�p����߁A�X�v�����N���[�z�njn��ʂ��đD��ɗ��܂����C���̐[����4.5m�ɂȂ�܂Œ������p������悤�w�������B�����ߑO6��30�����_�̑�3�D�q���͂̉��x�͐ێ�25�Ȃ���32�x�ł���A��3�D�q�Ƒ�4�D�q�̊Ԃ̉��x�͐ێ�45�x�ł������B�Ȃ��A�C���͐ێ�24�x�ł������B
�i�N�j�D���Ǘ����́A�����ߑO7��4�T���A�D���ɑ��A���[4m�ŃX�v�����N���[�z�njn���~����悤�w�����A�D���́A�����ߑO8��40���A���[4.1m�ŃX�v�����N���[�z�njn���~����悤�������B
�����ߑO9��10������̍�����3�R�����^���N�̑��[�l�́A3.01m�ł������B
�����ߑO10���ɂ͍������̉��x�́A�ێ�30�Ȃ���32�x�ɂȂ����B
�E �{�����̌�̏i�b�C1�A�b�n8�A10�A21�j
�i�A�j�D���Ǘ����́A����20���ߑO10��40���A�D���ɑ��A�Ĕ��h�~�̂��ߐ��[4m���ێ�����悤�w�������B
�i�C�j����22���ߑO2��50���A�X�v�����N���[�z�njn���~����ƂƂ��ɔr�����J�n���A�����ߌ�3���ɔr�������������B
�i�E�j�{�D�́A����23���ߑO5��30���A�T�U���v�g���`�ɓ������A���Έ��S�����̂��߁A�ڊ݂����A�T�U���v�g���`�ɂ����ẮA�D�����S�������iPort Control�j���A�ŏ��ɏ�D���A�������s�����B
�i�G�j�u���S�C�l�Ђ́A�������瓯��26���܂Ń��[�P�[�E�s�[�E�A���h�E�A�C�E�N���u��㗝����N���C�h�E�A���h�E�J���p�j�[�̎w�����A�{�D�ɏ�D���A���̌����̒������J�n�����i�ȉ��A�u���S�C�l�Ђ̎��̕��i�b�n8�j���u�u���S�C�l�E���|�[�g�v�Ƃ����B�j�B
�u���S�C�l�Ђ́A����28�����瓯��30���܂Ń��b�e���_���`�Ō������s���A�����A�n���u���N�`�̖{�D��Ō��������{�����B
�i�I�j���̑��A�J�j���K���E�����[�C�̌����ψ��́A����29���ߌ�2�����瓯��30���܂ŁA�������s�����B����ɁA�����C�����Z�l�Ƃ��đI�C���ꂽTaylor Marine TR Limted�̋����C���������́A����30���A�e������Ђ��Љ���B
�J�j���K���E�����[�C�́A���N11��1���A���ЂƋ����ŁA��3�D�q����������ꂽ�{�����̂̔������̋^��������{���R���e�i�����������B
�i�J�j�u���S�C�l�Ђ̃h�N�^�[�EN�E�T���_�[�X�́A����4���A���b�e���_���`�ɂ����Ė{�����̂̔������̋^��������{���R���e�i�̌����ɗ���������B
�i�Q�j�{�����̂̌���
�{�����̂̌����m�ɗ��t����؋��͂Ȃ����A���ɔF�肵���{�����̂̔����ɉ����āA�i1�j�J�j���K���E���|�[�g�y�уu���S�C�l�E���|�[�g�́A��������{�����̂̔����ӏ��́A��3�D�q�̑�23���E��8��E��2�w�ɐςݕt����ꂽ�{���R���e�i�����ł���ƌ��_�t���Ă��邱�Ɓi�b�C3�A�b�n8�j�A�i2�j��L2�F��̂Ƃ���A�{���e�ݕ��͂���������R���ΐ������ł���APSR�[80�͉R�������ɂ��Y������댯���ł��邱�ƁA�B�{�����̔����O����{���R���e�i�ɋߐڂ��鍶����3�R�����^���N�ŔR�����̉��M���p������Ă������ƁA�C�{���؋���A�{���R���e�i���ɂ͑��ɏo�̌����ƂȂ�댯�������������Ƃ͂��������Ȃ����Ƃ𑍍��l������ƁA�{�����̂̌����́A�{���e�ݕ��i����NA-125�������ȉ����������x���ႢPSR-80�j���A������3�R�����^���N����̔M�����X�ɒ~�ς��A���M���x�����~�M���x�������Ԃ��p�����āAPSR-80�̈ꕔ�����M���J�n���A���̂��߂ɖ{���e�ݕ��̎��ȉ����������x�����Ԃ���莞�Ԍp�����A���̌��ʁA�{���e�ݕ������ȕ������N�����ċɂ߂č����ƂȂ�A�{���e�ݕ������[����Ă����t�@�C�o�[�h�����ʂ�i�{�[������R�Ă����A�{���e�ݕ��ƂƂ��ɔ����������̂ł���Ɛ��F����̂������ł���B
�i�R�j�퍐�̎咣�ɂ���
�A �퍐�́A�{�����̂̌����ɂ��āA�i1�j�{�����͍̂�����3�R�����^���N�̔R�����̉��M�Ȃ����ߔM�̉e���ɂ��A�{���R���e�i�����������ԍ����ƂȂ�A�R���e�i���̑O���ɐςݕt�����Ă����t�F���g�y������R���K�X���������Đ��������������C�ɐÓd�C�̃X�p�[�N�������A�����������A���́i2�j������3�R�����^���N�����̉ߔM�ɂ�荶����3�R�����^���N�̊O�ǂ����������Ԑێ�100�x����ُ�ȍ����ƂȂ����e�����āA�{���R���e�i�������ێ�75�x�ȏ�̍�����Ԃ������ԑ����A�t�F���g�y������̉R���K�X�ɋN�����锚���y�і{���e�ݕ��̎��ȕ����ɂ�锭�M�ɂ��o�����ȂǂƎ咣����B
�C �������Ȃ���A���C�^�y�ѐ쐼�q�ɂ����o���ꂽ�R���e�i���ϕt�\�i��48��1�j�ɂ́A�{���R���e�i���Ƀt�F���g�y�������[����Ă����Ƃ̋L�ڂ͂Ȃ��A�t�F���g�y������{�����̂�������قǂ̉R���K�X���R�o�������Ƃ�t�F���g�y�����甭�������R���K�X���{�����̂̌����ł��邱�Ƃ��������킹��؋��͖R�����Ƃ����ׂ��ł��邩��A�퍐�̎咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�E �܂��A�퍐�́A������3�R�����^���N�̋��ɂ���Ė{���R���e�i���ύڂ���Ă�����3�D�q�̑�23���E��8��E��2�w���ُ�ȍ����ƂȂ��Ă����ȂǂƎ咣����B
�������A��L�F��̂Ƃ���A����16�N10��19���ߑO7��30���A������3�R�����^���N�̔R�����̎c���452.0�g�����������ƁA����20���ߑO5��15������̍�����3�R�����^���N�̑��[�l��3.10m�ł��������Ƃ��炷��ƁA������3�R�����^���N����ł��������Ƃ��������킹��؋��͂Ȃ��A�퍐�̎咣�͍̗p�ł��Ȃ��B
�G �����āA�{���؋���A��L�i�Q�j�ŔF�肵���Ƃ���ȊO�ɖ{�����̂̌����������I�ɐ��������鎖��͂��������Ȃ��B
�i�S�j����
���������āA�{�����̂̌����́A�{���e�ݕ��i����PSR�[80�j���A������3�R�����^���N����̔M��~�ς��Ĕ��M���J�n���A�܂�PSR-80�́A����NA�|125�̎��ȉ����������x�����Ԃ���莞�Ԍp���������߂ɖ{���e�ݕ������ꂼ�ꎩ�ȕ������J�n���A�{���S���e�i�����ɂ߂č����ƂȂ��āA�{���e�ݕ������[����Ă����t�@�C�o�[�h�����ʂ�i�{�[������R�Ă����A�{���e�ݕ��ƂƂ��ɔ����Ɏ��������̂ƔF�߂�̂������ł���B
4�@���_3�i���ΐӔC�@�̓K�p�̗L���j�ɂ���
�i�P�j�����@
�{���́A�_�ˍ`����I�����_�̃��b�e���_���Ɍ����čq�C����{�D�i�p�i�}�D�Ёj�ɐύڂ����댯���̉ב��l�ł���퍐�i���{�@�l�j���A���̒��Ӌ`���Ɉᔽ���A�{���e�ݕ����Ɋ댯���ł��邱�Ƃ������\���������A�D���ɖ{���e�ݕ����댯���ł��邱�Ƃ����m���Ȃ��������߁A�{���R���e�i���b��ł͂Ȃ��M���̋߂��ɐύڂ���Ă��܂��A���̂��߁A�n���C���q�s���ɖ{�����̂��������A�{�D�̐ωׁi���̉�l�́A�����̍��̖@�l�ł���B�j�ɑ��Q���������Ƃ��āA�����炪�퍐�ɑ��A�s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����������Ɋ�Â��A�������̎x�������߂Ă���i�ׂł���B
�{���̏����@�����肷���őO��ƂȂ�P�ʖ@���W�́A�s�@�s�ׂł���Ƃ���A�@�̓K�p�Ɋւ���ʑ��@�̎{�s���i����19�N1��1���j�O�ɉ��Q�s�ׂ̌��ʂ����������s�@�s�ׂɂ���Đ�������̐����y�ь��͂ɂ��ẮA�Ȃ��]�O�̗�ɂ�邩��i���@����3��4���j�A���@��11��1���̋K��ɂ��A�����ł��鎖���̔��������n�̖@���ɂ�邱�ƂƂȂ�B
�{���́A�퍐���䂪�����ɂ����Ė{���e�ݕ��̉^�����ϑ������ۂ̍�ז��͕s��ׂ̒��Ӌ`���ᔽ��₤���̂ł��邩��A���̌����ł��鎖���̔����n�i�s�@�s�גn�j�́A���{�ɍ݂�Ƃ����ׂ��ł���B���������āA�{���̏����@�́A���{�@�ł���i���̓_�ɂ��ẮA�����ҊԂɑ������Ȃ��B�j�B��������ƁA�{���ɂ����ẮA���ΐӔC�@�̓K�p�̗L�������ɂȂ�̂ł���B
�i�Q�j���ΐӔC�@�́A�u���@���S����m�K��n���m�ꍇ�j�n�V���K�p�Z�Y�A�V���Ύғ�d��i���ߎ��A���^���g�L�n���m����݃��Y�v�Ƃ��邾���ł����āA�K��̕�����A���̑Ώە��ɂ��A���̑Ώە������݂���n��ɂ��Ă�������肪�Ȃ��B
��������ƁA���{�@�������@�Ƃ�������́A���{�̗̊C�̊O���q�s���̑D���ɌW�鎸�ɂ��Ă����ΐӔC�@���K�p����邱�ƂɂȂ�B
���ΐӔC�@�����Ύ҂̖����ӔC���y�����Ă��闧�@��|�́A�i1�j�Ђ͎����̍��Y�����Ď����Ă��܂��̂��ʏ�ł��邩��A���l�����Ȃ̍�����Ŏ����Ȃ��悤�ɒ��ӂ�ӂ�Ȃ��̂ł���A���̏ꍇ�ɂ͗G�����ׂ��������ꍇ�����Ȃ��Ȃ����ƁA�i2�j��������Ђ����������Ƃ��́A��Е����̏A���h�{�݁A�Ђ̉ӏ��̓��H���̗��R�ʼnЂ��g�債�A���Q���������傫���L�͈͂ɂȂ邱�Ƃ�����̂ŁA���Ύ҂ɂ��̑S���̑��Q�̔����ӔC�S�����邱�Ƃ͍��ł��邱�ƁA�i3�j���̂悤�Ȏ����A�䂪���ł͎��ɂ������ӔC����Ȃ��Ƃ������K�����������ƂȂǂɂ���Ƃ����B��������ƁA�K��̕����ɔ����Ď��ΐӔC�@�̓K�p�͈͂���{�����́A���Ɍ��肷�闝�R�͂Ȃ��A�܂��A�D����Ώە��Ƃ��鎸�ɂ����ΐӔC�@�͓��R�ɓK�p�����Ƃ����ׂ��ł���B
�X�ɁA���Ƃ́A�߂��ĉ������A�Η͂̒P���ȔR�č�p�ɂ���č�����Ŏ����A���͏đ������邱�Ƃ������Ɖ����ׂ��ł��邩��A���Ζ��͍����̖Ŏ��Ⴕ���͑������̂��̂��Ζ�A�K�X�ޓ��̔����ɂ��ꍇ�ɂ́A���ΐӔC�@�̓K�p���Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B���̓_�ɂ��āANA�[125����PSR-80�̎��ȕ����������ɊY�����邩�ǂ���������ƁA�؋��i�b��6�j�ɂ��A�Ζ�͍��A����1�i�댯����1�j�Ƃ���A�K�X�ނ͍��A����2�i�댯����2�j�Ƃ���Ă���ƔF�߂邱�Ƃ��ł���̂ɑ��ANA-125�͎��R���ΐ������ł�����̂́A���Ȕ��M�������ɗ��܂�A�܂��APSR-80�͎��Ȕ����������ɊY�����A���A������4.1�i���A����4.1�͉R����L���邱�Ƃ��Ӗ�����B�j�ł�����̂́A�R�������ɗ��܂�̂ł����āA��������A�Ζ�A�K�X�ޓ��Ɠ����̊댯���͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�Ζ�A�K�X�ޓ������������ꍇ�Ɠ��l�ɖ{�����̂����ΐӔC�@�̓K�p�̑ΏۊO�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�R�j�܂��A�؋��i�b�C5�j�ɂ��A�{�����̌�̖{���R���e�i�ɗڂ����������Ƃ��F�߂���Ƃ���A������́A�{���e�����́A���ȕ����ɂ��A�_�f�̋������Ȃ��Ă��A���ʂ̒��f�K�X�A�M����o���ĕ�������̂ł����āA�����ɊY�����A�܂��A�_�����ۂł����āA�����R�Ăɂ͓�����Ȃ��Ǝ咣����B
�������A�؋��i��f�̂��́j�ɂ��A���̎������F�߂���B
�A PSR�[80�ɂ��ẮA�댯1���]���ؖ����ɂ����āA�u�K�X�o�[�i�[�Œ�����ƁA�����㕔�ɉ������f�����[�r���Y�������R�Ďc�Ԃ�����オ���Ă���B���̌㌃�����u�ԓI�ɕ�������B�v�A�u�f�����[�r�㕔�̒Y�������R�Ďc�ԕ����ŔR�Ă������ׁA�`�d���Ԃ͑���s�\�v�i����9�j�A�u�I�����W�F�̉����グ�ĉ��₩�ɔR�Ă���v�i����15�j�ƁA���i���S�f�[�^�V�[�g�i����13��1�j�ɂ����āA�u�R�ăK�X�ɂ́A�����_�����A���f�_���������܂܂��B�v�ƁAMSDS�ɂ����āA�u�C�A�Ռ��y�і��C���̑��̔M�ɂ��e�Ղɕ��͔R�Ă��邨���ꂪ����B�v�i����13��2�Ȃ���4�A6�A8�A10�A11�j�A�u�R�Ăɂ��L�ŃK�X���������邨���ꂪ����v�i����13��5�Ȃ���12�j�ƋL�ڂ���Ă���B
�C �܂��ANA-125�ɂ��ẮAMSDS�ɂ����āA�u�R�Ăɂ��L�ŃK�X���������鋰�ꂪ����v�i����14��4�Ȃ���8�j�A�u���Ȕ��M��������A�C�A�Ռ��A���C���̑��M���ɂ�蕪���E�R�Ă��鋰�ꂪ����v�i����14��9�A10�j�ƋL�ڂ���A�܂��A�댯���^���Ɋւ��鍑�A�����̎����y�щ��w�����̊댯���]���������ʕ��i����17�j�ɂ����āA���y�єR�Čp���������������Ƃ���Ă���B
�i�S�j�����ɂ��A�{���e�ݕ��́A������������A�R�Ă��鐫����L���Ă���ƔF�߂���Ƃ����ׂ��ł����āA��������i�ɂ����Ė{�����̂��Ђł��邱�Ƃ�O��Ƃ���咣���s���Ă������ƂɏƂ炷�ƁA�{�����̂́A�{���e�ݕ��̔R�ĕ��тɂ���ɔ����{���e�ݕ������[����Ă���������������̃t�@�C�o�[�h�����ʋy�ђi�{�[�����̉���ɂ�萶�������̂ł���Ƃ���̂������ł����āA������̏�L�咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��APSR-80�ɂ��ẮAMSDS�i����7�A8�A12�j�Łu�C�A�Ռ��A���C���̑��̔M���ɂ�蕪���E�������鋰�ꂪ����B�v�Ƃ���A�ꕔ�̊댯���]���ؖ����i����9�j�ł́A�������R��`�d����Ƃ���Ă��邪�A���̊댯���]���ؖ����i����8�A10��1�Ȃ���4�j�ł́A���R�y�є��R����������`�d���Ȃ��Ƃ���Ă����A��L�̂Ƃ���APSR-80�ɂ��ẮA�Ζ�A�K�X�ޓ��Ɠ����̊댯���͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{�����̂ɂ����āA���ΐӔC�@�̓K�p��ے肷�ׂ��������������Ƃ����ƂƂ͂ł��Ȃ����A�܂��A�Η͂̒P���ȔR�č�p���Ȃ������Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B
�i�T�j�ȏ�ɂ��A�{�����̂ɂ��ẮA���ΐӔC�@�̓K�p������Ƃ����ׂ��ł���B
5�@���_4�i�퍐�̏d�ߎ��̗L���j�ɂ���
�i�P�j��L4�ɂ��A�퍐�́A�{�����̂̔����ɂ��ďd�ߎ�������ꍇ�Ɍ����ĕs�@�s�אӔC�����ƂƂȂ�B
�i�Q�j�d�ߎ��̈Ӌ`
���ΐӔC�@�́A���Ύ҂̐ӔC���y�����邽�߁A��ʕs�@�s�ׂ̎�ϓI�v���Ƃ��ĉߎ��������Ă��閯�@709���̋K������̏ꍇ�ɂ͓K�p���Ȃ����ƂƂ��A�������Ύ҂ɏd��ȉߎ����������Ƃ��ɂ̂ݕs�@�s��̐ӔC���ׂ����Ƃ��K�肵���̂ł��邩��A���Ύ҂ɑ��s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����𐿋�����҂́A���Ύ҂ɏd��ȉߎ������������Ƃ𗧏��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA�����ɂ����d��ȉߎ��Ƃ́A�ʏ�l�ɗv���������x�̑����Ȓ��ӂ����Ȃ��ł��A�킸���̒��ӂ�������A���₷����@�L�Q�Ȍ��ʂ�\�����邱�Ƃ��ł����ꍇ�ł���̂ɁA���R����������������悤�ȁA�قƂ�nj̈ӂɋ߂����������ӌ��@�̏�Ԃ��w�����̂Ɖ�����̂������ł���i�ō��ُ��a32�N7��9����O���@�씻��1�O�f�j�Q�Ɓj�B
����́A�D�����S�@�̈ϔC������K�����ɂ��댯���̉ב��l�����̋`�����Ă���ꍇ�ł����Ă��A���l�ł���B
�i�R�j�؋��i��3�A4�A16�Ȃ���18�A37�A57�A����12�A17�A�ؐl�������A�ؐl���ËԈ�Y�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���̎������F�߂���B
�A �i�A�j�퍐�́A���a62�N����ȍ~�A�⏕�Q���l�_�C�g�[����NA-125���p���I�ɍw�����ĊC�O�ɗA�o���Ă����Ƃ���A�����A�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�퍐�ɑ��ANA-125�ɂ��āA������i�̌��������Ȃ��܂܁A���A�ԍ�3226�̎��Ȕ����������ɊY������Ƃ̏�����Ă����B
�i�C�j�⏕�Q���l�_�C�g�[�́ANA-125�������^���ɂ����Ă͏��h�@��댯���Ƃ��Ď�舵���Ă��Ȃ��̂ɁA�A�o�ɂ��Ă͊댯���Ƃ��Ď�舵���邱�Ƃɋ^�������A���{�C�����苦��Ɍ������˗������Ƃ���A���{�C�����苦��́A����15�N12��2���ANA-125�ɂ��A��K���ɒ�߂�ꂽ���Ȕ�������������̏��O�v���ł���u50Kg�̗A�����ɂ�����SADT�l�i���ȉ����������x�j��75��C���镨�v�ɊY������̂ŁA���Ȕ����������ɊY�����Ȃ��Ɣ��肵���i��4�j�B
�i�E�j�����ŁA�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�퍐�ɑ��āANA-125�͊댯���ɊY�����Ȃ��Ɛ���������ANA-125�̃e�N�j�J���f�[�^�i��2�j�A����15�N10��24���t����NA-125��MSDS�i��3�j�y�ѓ��N12��2���t���̊댯���]���ؖ����i��4�j����t�����B���e�N�j�J���f�[�^�i��2�j�ɂ́A���x90.0%�ȏ�A����7.0%�ȉ��ƁA�M�����Ƃ��āu�M��������ƁA130��C���炢���璂�f���o�����X�ɕ�������B�v�ƁA�w�������Ƃ��āu�����A���˓������͌u�����̏Ǝ˂�����A��Ï��ɕۊǂ���v�Ƃ��ꂼ��L�ڂ���A��MSDS�i��3�j�ɂ́A�u���{�ɂ�����댯�L�Q�����ނ̖��́v���Ɂu���ފ�ɊY�����Ȃ��v�ƁA�u�A����̏��v�́u���A���ށv���y�сu���A�ԍ��v���ɂ�������u�Y�����Ȃ��B�v�ƁA���̂ق��u�A����̏��v�Ƃ��āu�e��̔j���Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB���C�A�]�|�A�����A�Փ˓��̗��\�Ȏ�舵���͐�ɔ����邱�ƁB�����̊W�@�߂ɏ]�����ƁB�v�ƁA�u���萫�y�є������v�̗��Ɂu���ۊ댯���^���ɂ����鎩�Ȕ����������i���A����4.1�A���A�ԍ�3226�j�ł͂Ȃ��B�v�Ƃ��ꂼ��L�ڂ���A���댯���]���ؖ����i��4�j�ɂ́A�u�����E�g���v�̗��Ɂu�ܗL��90.0�`95.0%�A����6.0�`7.0%�v�ƋL�ڂ���Ă����B
�i�G�j����āA�퍐�́ANA-125���댯���Ƃ��Ď�舵�������A�{�����̑O�ADKSH�ɑ��Ĕ�����NA-125���v3��Kg�̂�������15�N12��16�����畽��16�N8��16���܂ł̊ԂɊC��A�����ꂽ5��NA�[125�i�e5000Kg�A���v2��5000Kg�j�́A�Ў��̓����N�������ƂȂ��A���S�ɗA�����ꂽ�B
�i�I�j�Ȃ��A�{�����̑O�ɕ⏕�Q���l�_�C�g�[���퍐�Ɍ�t���Ă���NA�\125�Ɋւ��铯�N9��10���t���u���͏ؖ����v�ɂ́A�����ԍ����Ƃ̐��ʁA���e�ʁA���q�ʁA���x�A�����y�ѐ��������L�ڂ���Ă����B
�i�J�j�퍐�́A�{�����̑O�ANA-125�ɂ��āA��L�i�A�j�Ȃ����i�E�j�y�сi�I�j�ȊO�̏��͓��肵�Ă��Ȃ������B
�i�L�jNA-125���댯���i���Ȕ��M�������Ƃ��Ă̎��R���ΐ������j�ɊY�����邱�Ƃ́A�J���e�b�N�쐬�̕���17�N12��14���t���u�댯���A���Ɋւ��鍑�A�����̎����y�щ��w�����̊댯���]���������ʕ��v�i����17�j�ɂ���ď��߂Ĕ��������B
�C �i�A�j�{�����̑O�A�⏕�Q���l�_�C�g�[�́A�퍐�ɑ��āAPSR-80�͊댯���ɊY�����Ȃ��Ɛ������Ă���A�⏕�Q���l�_�C�g�[���A�퍐�Ɍ�t����PSR-80�̕���16�N9��15���t�����͏ؖ����i��16�j�ɂ́A�u�ۊ�:�Ռ����A��������߂��e��ŗ�Ï��ɕۊǁv�ƋL�ڂ���APSR�[80�̃e�N�j�J���E�f�[�^�i��17�j�ɂ́A�M�����Ƃ��āu�M�����130��C���炢���珙�X�ɕ������A���f�K�X������v�ƁA�w�������Ƃ��āA�����A���˓������͌u�����̏Ǝ˂�����A��Ï��ɕۊǂ���v�ƋL�ڂ���APSR�[80�̕���8�N��MSDS�i��18�j�ɂ́A�u���{�ɂ�����댯�L�Q�����ނ̖��́v���Ɂu���ފ�ɊY�����Ȃ��v�ƁA�Z�_�́A�u130��C�i����_�j�v�ƁA�u�A����̏��v�Ƃ��āu�e��̔j���Ȃ����Ƃ��m���߂邱�ƁB���C�A�]�|�A�����A�Փ˓��̗��\�Ȏ�舵���͐�ɔ����邱�ƁB�v�Ƃ��ꂼ��L�ڂ���A�u���A���ށv���y�сu���A�ԍ��v�����тɁu���Ȕ������A�������v���͂�������Ƃ���Ă������A�����A�u�����I���w�I�댯���v���ɂ́u�C�A�Ռ��A���C�A���̑��M���ɂ��A�e�Ղɕ����E�������鋰�ꂪ����B�v�ƁA�u���萫�E�������v���Ɂu���ɂ�蕪�����A�A���J���Ɣ������ĕi�����N�������ꂪ����v�Ƃ��ꂼ��L�ڂ���Ă����B
�i�C�j�퍐�́A�{�����̂Ɏ���܂łɁAPSR-80�ɂ��āA����14�N2���ȍ~�C��^����24��ϑ��������A���̍ہA�Ў��̓���1�x���Ȃ������B�Ȃ��A�퍐�́A�{�����̑O�APSR-80�ɂ��āA��L�i�A�j�ȊO�̏��͓��肵�Ă��Ȃ������B
�i�S�j�ȏ��O��Ƃ��āA�퍐�̏d�ߎ��̗L���ɂ��Č�������ƁA�퍐���A�{�����̑O�A�⏕�Q���l�_�C�g�[���瓾�Ă����{���e�ݕ��ɂ��Ă̏��́A��������댯���ɊY�����Ȃ��Ɨ����ł�����e�ł���A���w��������舵���Ƃ͂����A���w�����̐����҂łȂ����Ђɂ����Ȃ��퍐�ɂ����āA�����҂�����ꂽ���Y����ϋɓI�ɋ^���āA���̐��m�����X�ɒ������ׂ��`�����Ă����Ƃ������Ƃ͂ł����A����ɁA�퍐���A�{���e�ݕ��ɂ��āA��댯���Ƃ��āA���Ȃ��Ƃ�5��A�C�O�ւ̖����̂̉^�����т�L���Ă������ƂɏƂ炷�ƁA�퍐���{���e�ݕ����Ɋ댯���ł���|�̕\���������A�{�D�̑D���ɂ����̎|�̏��������Ȃ��������Ƃɂ��āA�قƂ�nj̈ӂɋ߂����������ӌ��@�̏�ԂƂ�����܂ł̉ߎ����������Ƃ͓���F�߂��Ȃ��̂ł����āA�퍐�ɏd�ߎ����������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
���̓_�A�{���؋���A�퍐���APSR-80�̉^�����@�ɂ��āA�⏕�Q���l�_�C�g�[�Ɠd�q���[���ŏ����������Ă������Ƃ����������邪�i�b��84�A85�A��59�j�A����́APSR�[80���댯���ł��邱�Ƃ�O��ɂ������̂ł͂Ȃ��APSR�[80�̕i���̗�O���ɒu�������Ƃ�ł����āi�ؐl���Áj�A��L���f�����E�������̂ł͂Ȃ��B
6�@���_
�ȏ�̎���ŁA������̐����́A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A���R���Ȃ�����A����������p���邱�ƂƂ��A�i�ה�p�i�⏕�Q���ɂ���Đ�������p���܂ށB�j�̕��S�ɂ��A�����i�ז@61����K�p���āA�啶�̂Ƃ��蔻������B
�����n���ٔ���������23��
�ٔ����ٔ����@�@�@���@�@���@�@�@�@�@�@�@��
�ٔ����@�@�@�@�@�@���@�@�i�@�@�@���@��@�Y
�ٔ����@�@�@�@�@�@�́@�@��@�@�@��@�@�@�Y
�i�ʎ��j
���@�@���@�@�ځ@�@�^
�����s���c��ۂ̓��꒚��2��1��
|
��1������������2
������������4��������
|
�����C������Еی��������
|
|
����\�ґ�\�����
|
���F�p�v
|
�����s������V���27��2��
|
��1������������2
������������4��������
|
�O��Z�F�C��Еی��������
|
|
����\�ґ�\�����
|
�]���q��
|
���s�k�搼�V���l����15��10��
|
��1������������2
������������4��������
|
�j�c�Z�C���a���Q�ی��������
|
|
����\�ґ�\�����
|
���R��N
|
�����s�V�h�搼�V�h�꒚��26��1��
|
��1������������2��������
|
������Б��Q�ی��W���p��
|
|
����\�ґ�\�����
|
����_�u
|
�����s�a�J��b����꒚��28��1��
|
��1������������2��������
|
�����������Q�ی��������
|
|
����\�ґ�\�����
|
���ʐ��V
|
���s�������D��꒚��18�ԂP1��
|
��1������������2��������
|
�x�m�ЊC��ی��������
|
|
����\�ґ�\�����
|
�r�W�����R�X���V���q
|
�A�����������h���s���[�f���z�[���E�X�g���[�g150
|
��1������������2��������
|
�g�[�L���[�E�}�����E���[���b�p�E
�C���V���A�����X�E���~�e�b�h
|
|
����\�ґ�\�����
|
�r�W�����R�X���V���q
|
�p�i�}���a���p�i�}�s53�ԊX�A�[�o�i�C�[�[�V�����I�o���I�X�C�X�^���[16�K
|
��3��������
|
�G�k���C�P�[�E�A���O
�X�E�R�[�|���[�V����
|
|
����\�ґ�\�����
|
�������T
|
�����s���c������֎O����7��3��
|
��4��������
|
���{�������Q�ی��������
|
|
����\�ґ�\�����
|
�����@��
|
�A�����������h���s�r�V���b�v�X�Q�[�g155�@4�K
|
��4��������
|
�\���|�E�W���p���E�C���V���A��
���X�E�J���p�j�[�E�I�u
���[���b�p�E���~�e�b�h
|
|
����\�҃W�F�l��
���E�}�l�[�W���[
|
�~�c���E�R�_�}
|
�X�C�X�A�M�o�[�[���s�A�F�b�V�F���O���[�x��21
|
��4��������
|
�o�����[�E�C���V���A�����X�E
�J���p�j�[�E���~�e�b�h
|
|
����\�҃��@�C�X
�E�v���W�f���g
|
�e�I�t�B���E�n�[�t�i�[
|
�X�E�F�[�f�������X�g�b�N�z�����s50�G�X�C�[�[105
|
��4��������
|
���[���X�t�H���Z�[�N����
�K�[�E�T�b�N�E�t�H���Z�[�N
�����O�T�b�N�e�B�{���O
|
|
����\�Ҋ�ƕی����ƕ��咷
|
���[�Y�E�A���_�[�\��
|
�I�����_�����A���X�e���t�F�[���s�v���t�F�c�T�[�E�o�r���N���[��1
|
��4��������
|
�t�H�[�e�B�X�E�R�[�|���[�g
�C���V���A�����X�E�G�k�E�u�C
|
|
����\�҃X�y�V�����X�g�E
�N���[���Y�E�A�W���X�^�[
|
�}���Z���E�t�@���E�r�[�X�g
|
�I�����_�����n�[�O�s�G�C�S���v���C��50
|
��4��������
|
�G�C�S���E�V���[�f�t�F��
�[�[�P�����O�E�G�k�E�u�C
|
|
����\�ґ�\�����
|
�G�X�E�_�u�����[
�E�V�[�E���[���b�c
|
�h�C�c�A�M���a���P�����s�R���j�A�E�A���[10�[20
|
��4��������
|
�A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\����
�\�V�����Y�E�j�[�_�[���b�T��
�N�E�h�C�b�`�F�����g�E�f�A
�E�A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\����
�\�V�����Y�E�A�V���A�����X
|
|
����\�Ҏ��s����
|
�n�C�P�E�V���e�B���[
|
�h�C�c�A�M���a���}���n�C���s�A�E�O�X�^�A�����[�Q66
|
��4��������
|
�}���n�C�}�[�E�t�F�A�Y�B�b
�q�����O�E�A�N�c�B
�G���Q�[���V���t�g
|
|
����\��
|
�J�[���X�e���E���[�Q
|
�h�C�c�A�M���a���n���u���N�s�n�C�f���J���v�X�E�F�O102
|
��4��������
|
�N���o�O�[���W�X�e�B�b�N�E
�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�[
�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g
|
|
����\��
|
�z���X�g�E�N���}�[
|
�h�C�c�A�M���a���n���u���N�s���[�o�[�Z�[�����O32
|
��4��������
|
�r�N�g���A�E�t�F�A�Y�B�b
�q�����O�Y�E�G�C�W�[
|
|
����\�҃N���[
���Y�E�}�l�[�W���[
|
�A���h���A�E�n�[�y���V�����K�[
|
�h�C�c�A�M���a���n�m�[�o�[�s���[�\�[�X�g2
|
��4��������
|
�G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O
�E�C���h�D�X�g�D���[�E�t�F�A
�Y�B�b�q�����O�E�G�C�W�[
|
|
����\�Ҏ����
|
�J�[���[�Q���n���g�E���b�c�i�[
|
�h�C�c�A�M���a���n���u���N�s�A�h�~�����^�c�X�g���X67
|
��4��������
|
�R���h�A�E�A���Q�}�C�l�E
�t�F�A�Y�C�c�q�����O�Y�[�A
�N�c�B�G���Q�[���V���t�g
|
|
����\�҃w�b�h�E�N���[�N
|
�s�[�^�[�E�W���b�v
|
�A�������A�b�N�X�u���b�W�s�I�b�N�X�t�H�[�h�E���[�h�@�u���b�W�E�n�E�X
|
��4��������
|
�[���b�N�X�E���~�e�b�h
|
|
����\�ґ�\�����
|
�G���E�A�[���E�t�F�X�^
|
�A�������E�[�X�^�[�s�o�b�W���[�X�E�h���C�u
|
��4��������
|
���}�U�L�E�}�U�b�N�E
���[�P�[�E���~�e�b�h
|
|
����\�҃}�l�[�W
���O�E�f�B���N�^�[
|
�f�C�r�b�h�E�q���[�Y�E�W���b�N
|
�ȏ�
�i�ʎ��j
���@���@��@���@�l�@�ځ@�^
��1����������i�ב㗝�l�ٌ�m ���@�@�@��@�@�@��@�@�@��
��1����������i�ו��㗝�l�ٌ�m����2�����A��4�����y�ё�5����������i�ב㗝�l�ٌ�m
���@�@�@�c�@�@�@��@�@�@��
�� ���@�X�@�@�@�@�L�@�@�@�l
�� �y�@�@�@�c�@�@�@�@�@�@�@��
��3���������i�ב㗝�l�ٌ�m �@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�G
�� �c�@�@�@���@�@�@�f�@�@�@��
�� �@�@�@���@�@�@���@�@�@��'
���i�ו��㗝�l�ٌ�m �߁@�@�@���@�@�@�F�@�K�@�q
�ȏ�
�i�ʎ��j
��@���@���@�ځ@�^
�����s�`��O�c�O����4��19��
���Ȃ�����5�����퍐 DKSH�W���p���������
(�������E���{�V���x���w�O�i�[�������)
����\�ґ�\����� ���H���t�K���O�E
�V�����c�F���o�b�n
���i�ב㗝�l���ٌ�m ���@�@�@�ˁ@�@�@�@�@�@�@��
�� �R�@�@�@���@�@�@�^�@��@�Y
���i�ו��㗝�l�ٌ�m �i�@�@�@��@�@�@�I�@�@�@��
�� ��@�@�@�r�@�@�@�I�@�@�@�q
�� �q�@�@�@���@�@�@�P�@�@�@�K
�� �H�@�@�@�t�@�@�@���@�@�@�b
��1�Ȃ�����3����
�퍐�i�ו��㗝�l�ٌ�m �c�@�@�@���@�@�@���@�m�@�q
���s�ߌ����c��{�O����1��7��
��1�Ȃ�����5����
�퍐�⏕�Q���l �_�C�g�[�P�~�b�N�X�������
����\�ґ�\����� ���@�@�@���@�@�@��@�@�@�O
���i�ב㗝�l�ٌ�m ���@�@�@�J�@�@�@�j�@�@�@�N
�� ���@�@�@�V�@�@�@�N�@�@�@��
�� ��@�@�@�с@�@�@���@�@�@�L
�����s�`��Ōܒ���10��1��
��1�Ȃ�����5����
�퍐�⏕�Q���l �p�i���s�i�E���[���h�E�g����
�X�|�[�g�E�W���p���������
����\�ґ�\����� �A���h���A�X�E�x���P
�X�C�X�A�M�o�[�[���s�t�B�A�h�D�N�X�g���b�Z42
��1�Ȃ���5����
�퍐�⏕�Q���l �p���e�i�[�E���~�e�b�h
����\�Ҏ������c�� ���j�J�E���o�[�E�o�E�}��
��L2���i�ב㗝�l�ٌ�m ���@�@�@��@�@�@�F�@�@�@�V
���i�ו��㗝�l�ٌ�m ���@�@�@�V�@�@�@���@��@�Y
�ȏ�
�i�ʎ��j
���@�@���@�@�ځ@�@�^
1�@��1����
�i��ʓI�����j
�i1�j �퍐�́A���������C������Еی�������Ђɑ��A90��4185.10���[���A5140��6745�~�A38��1585.04�X�C�X�t�����A14��0O16.62�č��h���y��5647.57�X�^�[�����O�E�|���h���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i2�j �퍐�́A����������Б��Q�ی��W���p���ɑ��A37��3529.05���[���A790����605�~�A2��5439.O0�X�C�X�t�����y��7��2246.13�č��h�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x��:�ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i3�j �퍐�́A�����O��Z�F�C��Еی�������Ђɑ��A11��4786.30���[���A485��4047�~�A7��6317.01�X�C�X�t�����y��1��4385.38�č��h�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i4�j �퍐�́A���������������Q�ی�������Ђɑ��A7��9402.67���[���A229��5025�~�A2��5439.00�X�C�X�t�����y��4795.13�č��h�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i5�j �퍐�́A�����j�b�Z�C���a���Q�ی�������Ђɑ�5��1278.05���[���y��84��3832�~���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i6�j �퍐�́A�����x�m�ЊC��ی�������Ђɑ�5312�[30���[���y��8��7419�~���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i7�j �퍐�́A�����g�[�L���[�E�}�����E���[���b�p�E�C���V���A�����X�E���~�e�c�h�ɑ�21��4905.97���[���y��353��6493�~���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i�\���I�����j
�i1�j �퍐�́A���������C������Еی�������Ђɑ�2��2651��8920�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i2�j �퍐�́A����������Б��Q�ی��W���p���ɑ�6960��7603�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i3�j �퍐�́A�����O��Z�F�C��Еی�������Ђɑ�2889��4603�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i4�j �퍐�́A���������������Q�ی�������Ђɑ�1594��5209�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i5�j �퍐�́A�����j�c�Z�C���a���Q�ی�������Ђɑ�786��0690�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i6�j �퍐�́A�����x�m�ЊC��ی�������Ђɑ�82��7157�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i7�j �퍐�́A�����g�[�L���[�E�}�����E���[���b�p�E�C���V���A�����X�E���~�e�b�h�ɑ�3297��6461�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
2�@��2����
�i��ʓI�����j
�i1�j �퍐�́A�����O��Z�F�C��Еی�������Ђɑ��A2997��4962�~�A33��0139.75���[���y��16��2285.00�X�E�F�[�f���E�N���[�l���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i2�j �퍐�́A�����x�m�ЊC��ی�������Ђɑ��A72��o287�~�y��4��3743.89���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i3�j �퍐�́A���������C������Еی�������Ђɑ��A1213��5804�~�y��2��5842.80���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i4�j �퍐�́A���������������Q�ی�������Ђɑ��A106��3013�~�y��1��7146.11���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i5�j �퍐�́A����������Б��Q�ی��W���p���ɑ��A228��1965�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i6�j �퍐�́A�����j�b�Z�C���a���Q�ی�������Ђɑ��A7��7134�~�y��4684.42���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i�\���I�����j
�i1�j �퍐�́A�����O��Z�F�C��Еی�������Ђɑ��A8733��8046�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i2�j �퍐�́A�����x�m�ЊC��ی�������Ђɑ��A792��3156�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i3�j �퍐�́A���������C������Еی�������Ђɑ��A1639��1079�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i4�j �퍐�́A���������������Q�ی�������Ђɑ��A388��6291�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊��q�ɂ��������x�����B
�i5�j �퍐�́A����������Б��Q�ی��W���p���ɑ��A228��1965�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i6�j �퍐�́A�����j�b�Z�C���a���Q�ی�������Ђɑ��A84��8470�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
3�@��3����
�퍐�́A�����G�k���C�P�[�E�A���O�X�E�R�[�|���[�V�����ɑ��A2��6734��6750�~�y�т���ɑ��镽��17�N10��28������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
4�@��4����
�i��ʓI�����j
�i1�j
�퍐�́A�������{�������Q�ی�������Ђɑ��A4856��7390�~�y��2086.0O���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i2�j
�퍐�́A���������C������Еی�������Ђɑ��A1236��1691�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i3�j
�퍐�́A�����O��Z�F�C��Еی�������Ђɑ��A206��0283�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i4�j
�퍐�́A�����j�b�Z�C���a���Q�ی�������Ђɑ��A206��0283�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i5�j
�퍐�́A�����\���|�E�W���p���E�C���V���A�����X�E�J���p�j�[�E�I�u�E���[���c�p�E���~�e�b�h�ɑ��A549��7758�~�y��32��8931.34���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ悤�������x�����B
�i6�j
�퍐�́A�����t�H�[�e�B�X�E�R�[�|���[�g�E�C���V���A�����X�E�G�k�E�u�C�ɑ��A69��2714�~�y��4��1445.15���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i7�j
�퍐�́A�����G�C�S���E�V���[�f�t�F���[�[�[�P�����O�E�G�k�E�u�C�ɑ��A69��2714�~�y��4��1445.15���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i8�j
�퍐�́A�����g���L���[�E�}�����E���[���b�p�E�C���V���A�����X�E���~�e�b�h�ɑ��A69��2714�~�y��4��1445�[15���[�����тɂ���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i9�j
�퍐�́A�����o�����[�E�C���V���A�����X�E�J���p�j�[�E���~�e�b�h�ɑ��A195��2178�~�y��19��5687.40�X�C�X�t�������тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i10�j �퍐�́A�����A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\�����[�\���Y�E�j�[�_�[���b�T���N�E�h�C�b�`�F�����g�E�f�A�E�A�N�T�E�R�[�|���[�g
�\�����[�V�����Y�E�A�V���A�����X�ɑ��A412��7009�~�y��24��6919.28���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i11�j �퍐�́A�����}���n�C�}�[�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�E�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g�ɑ��A85��9794�~�y��5��1441.52���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i12�j �퍐�́A�����N���o�O�[���W�X�e�C�c�N�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�[�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g�ɑ��A85��9794�~�y��5��1441.52���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i13�j �퍐�́A�����r�N�g���A�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�ɑ��A51��5876�~�y��3��0864.91���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i14�j ���퍐�́A�����G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O�E�C���h�D�X�g�D���[�E�t�F�@�Y�B�b�q�����O�E�G�C�W�[�ɑ��A34��3917�~�y��2��0576.60���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i15�j �퍐�́A�����R���h�A�E�A���Q�}�C�l�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�[�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g�ɑ��A17��1958�~�y��1��o288.30���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i16�j �퍐�́A�������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�E�T�b�N�E�t�H���Z�[�N�����O�T�b�N�e�B�{���O�ɑ��A106��8564�~�y��57��7602.00�X�E�F�[�f�V�E�N���[�l���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i17�j �퍐�́A�����[���b�N�X�E���~�e�b�h�ɑ��A323��1932�~�y��4��5318.80���[�����тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i�\���I�����j
�i1�j
�퍐�́A�������{�������Q�ۏ�������Ђɑ��A4906��6470�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i2�j
�퍐�́A�����\���|�E�W���p���E�C���V���A�����X�E�J���p�j�[�E�I�u�E�ꃈ�[���b�p�E���~�e�b�h�ɑ��A6047��5342�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i3�j
�퍐�́A�����t�I�[�e�B�X�E�R�[�|���[�g�E�C���V���A�����X�E�G�k�E�u�C�ɑ��A761��9856�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i4�j
�퍐�́A�����G�C�S���E�V���[�f�t�F���[�[�[�P�����O�E�G�k�E�u�C�ɑ��A761��98�E56�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i5�j
�퍐�́A�����g�[�L���[�E�}�����E���[�[���b�p�E�C���V���A�����X�E���~�e�b�h�ɑ��A761��9856�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i6�j
�퍐�́A�����o�����[�E�C���V���A�����X�E�J���p�j�[�E���~�e�b�h�ɑ��A2147��3953�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i7�j
�퍐�́A�����A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\�����[�\���Y�E�j�[�_�[���b�T���N�{�h�C�b�`�F�����g�E�f�[�A�E�A�N�T�E�R�[�|���[�g�E�\�����[�V�����Y�E�A�V���A�����X�ɑ��A4539��7097�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i8�j
�퍐�́A�����}���n�C�}�[�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�E�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g�ɑ��A945��7730�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i9�j
�퍐�́A�����N���o�O�[���W�X�e�C�c�N�E�t�F�A�Y�B�W�q�����O�Y�[�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g�ɑ��A945��7730�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i10�j �퍐�́A�����r�N�g���A�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�E�G�C�W�[�ɑ��A567��4637�~���т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i11�j �퍐�́A�����G�C�`�f�B�[�A�C�[�Q�[�����O�E�C���h�D�X�g�D���[��E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�E�G�C�W�[�ɑ��A378��3090�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i12�j �퍐�́A�����S���h�A�E�A���Q�}�C�l�E�t�F�A�Y�B�b�q�����O�Y�[�A�N�c�B�G���Q�[���V���t�g�ɑ��A189��1544�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i13�j �퍐�́A�������[���X�t�H���Z�[�N�����K�[�E�T�b�N�E�t�H���Z�[�N�����O�T�b�N�e�B�{���O�ɑ��A1175��4201�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�i14�j �퍐�́A�����[���c�N�X�E���~�e�b�h�ɑ��A1080��6516�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
5�@��5����
�i��ʓI�����j
�퍐�́A�������}�U�L�E�}�U�b�N�E���[�P�[�E���~�e�b�h�ɑ��A1324��6698�~�y��82��8281���[�ꃍ���тɂ����ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B�i�\���I�����j
�퍐�́A�������}�U�L�E�}�U�b�N.���[�P�[�E���~�e�b�h�ɑ��A1��4571��3678�~�y�т���ɑ��镽��16�N10��20������x���ς݂܂ŔN5���̊����ɂ��������x�����B
�ȏ�