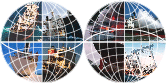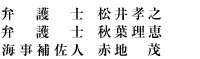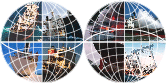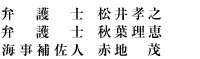|

押船G丸損害賠償請求紛議仲裁判断
申立人
|

|
買主・傭船者(在広島県)
|
被申立人
|

|
売主・船主(在大分県)
|
被申立人代理人弁護士 松井孝之
|
上記当事者間における平成10年1月24日付押船G丸売買契約及び同日付G丸裸傭船契約に関する不当利得を巡る紛議につき、社団法人日本海運集会所海事仲裁規則により選任された下名仲裁人は、慎重審議の結果次のとおり判断する。
主文
- 申立人の請求を棄却する。
- 仲裁費用は金1,071,000円(消費税を含む)とし、両当事者折半負担とする。
- 仲裁判断に関する管轄裁判所は神戸地方裁判所とする。
事実
第1.当事者の請求
(申立人)
- 被申立人は申立人に対し、金25,300,000円及びこれに対する仲裁判断の日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
- 仲裁費用は被申立人の負担とする。
(被申立人)
- 申立人の請求を棄却する。
- 仲裁費用は申立人の負担とする。
第2.事実及び当事者の主張の概要
(申立人)
- 申立人は被申立人との間において、平成10年1月24日付押船G丸(以下「本船」という)について売買契約(以下「売買契約」という。甲第1号証)を締結した。売買契約の主要内容は次のとおりである。
|
売買価額
|

|
金30,700,000円(内建造引当権金17,550,000円)
|
|
手付金
|
金4,000,000円
|
|
残代金
|
金26,700,000円
|
|
消費税
|
内税とする。
|
引渡し場所
|
大分県佐伯市
|
引渡し期間
|
平成9年12月28日より平成10年2月28日まで
|
本船売買価格の支払方法については別紙協定書を作成する。
内航裸傭船契約を締結する。
本売買契約が日本内航海運組合総連合会の承認がえられなかった場合は本契約を無償解約とする。
- 本船売買代金の支払い方法は、平成10年1月24日付協定書(甲第3号証)により次のとおりである。
毎月15日を期日とする額面200万円也の約束手形を2ヵ月おきの(平成10年4月、6月、8月、10月、12月、平成11年2月、4月)月末迄に2枚づつ売り主に渡す事とする。又最終平成11年4月末の手形は5月15日期日額面270万円也の約束手形1枚とする。
- 申立人は代金支払いを担保とするため、被申立人との間で本船につき、売買契約締結と同時に裸傭船契約(以下「裸傭船契約」という、甲第2号証)を締結した。裸傭船契約第10条には傭船者は自己の費用をもって船主を受取人とする保険契約を締結し、本契約期問中有効に存続させなければならないと定められている。
- 申立人は、自己の兄弟会社である申立外有限会社Aによって、平成11年2月2日申立外損害保険会社(以下「B保険会杜」という)と本船について被申立人を被保険者とする平水区域第8号の船舶及び船主責任保険契約を締結した。
- 本船は平成11年2月3日午前9時30分頃大柿から鹿児島県串木野港に向け航海中、愛媛県磯崎夢水岬西側北緯33度32分東経132度24分付近で座礁し、沈没した。
- 被申立人は本船が沈没した結果、B保険会社から28,000,000円の保険金と日本内航海運組合総連合会(以下「総連合会」という)から20,000,000円の建造引当金合計48,000,000円を受領した。
- 申立人は、本船の売買代金として契約締結日に4,000,000円、その後4,000,000円の約束手形を決済したので、支払い済み代金総額は8,000,000円である。
- 申立人は、平成11年5月頃被申立人に対して6及び7に記載した金額の合計額56,000,000円と本船売買価格30,700,000円との差額25,300,000円を請求したところ、被申立人はこれを拒んだ。被申立人のそのような行為は、刑法上業務上横領に該当する。
- よって、申立人は被申立人の不当利得に基づき金25,300,000円及びこれに対する仲裁判断の日から完済まで年5分の割合の金員を請求する。
- 売買契約第3条第3項に残代金並びに消費税の受取りと同時に本船の所有権移転登記手続に必要な一切の書類等を買主に引き渡すと定められ、第11条で本船の固定資産税は本船引渡し月分まで売主、翌月から買主が負担すると定められていることから、協定書の所有権移転とは、登記手続のことをいうことは明らかである。即ち、売買契約締結と同時に所有権は買主に移転するが、第三者への対抗要件としての登記は残代金支払いと同時に行うという意味である。このことは裸傭船契約に傭船料を0円と定めたことからも明白である。
- 本船の保険は、売買代金残を担保とするため、裸傭船契約を締結し、被申立入を保険金受取人とする保険をかけたもので、一種の譲渡担保類似保険であるから、当事者間で精算しなければならない。
- 申立人が保険金受取人となっているのは、保険契約上のものであるから、受領した保険金については、売買代金を差し引いて残額を申立人に返還すべき精算義務が被申立人にある。売買代金は手付金4,000,000円と残金を分割で支払うことを、当事者間で合意したのであるから、仮に事故がなければ、1年以上にわたって残代金を受領することによって被申立入は満足したはずである。たまたま事故によって本船が沈没したために船価以上の保険金と手付金及び分割金も返還しないのは、精算義務に反し信義則上許されるものではない。
(被申立人)
- 売買契約(甲第1号証)は裸傭船契約(甲第2号証)と協定書(甲第3号証)とともに締結されたものであるから、これら諸契約は総合的に判断されるべきであり、本件は、買取権付裸傭船契約と考えるべきである。したがって、申立人が被申立人に支払ったものはすべて裸傭船料として支払われたものであり、本件諸契約は、すべて裸傭船契約第12条により終了したものである。
- 特に協定書第4条には、本船の所有権は、「売買代金が全額決済された時点」で移転する、と極めて明確に記載されている、さらに、売買契約の特約第3項には、「本売買契約が日本内航海運総連合会の承認がえられなかった場合は本契約は無償解約とする。」と規定されている。本件事故当時、本件売買に関して、総連合会の承認は得られていなかった。
- 被申立人は、B保険会社より金28,023,375円(保険金より未払い保険料を控除した額)を受け取った。被申立人は、総連合会から建造引当金として20,728,305円を受け取った。本船の座礁事故による船主の責任は、B保険会社の「汚染損害に関する船主責任追加担保特別条項」によりカバーされたが、同保険条項には免責金額が500,000円設定されていて、この免責金額は被申立人が負担した。
- 本船の所有権者が被申立人であったことは、協定書第4条により明らかである。被申立人が本船所有者として保険金及び建造引当金を取得するのは、当然であり、業務上横領罪が成立しないのも明らかである。
- 申立人は、8,000,000円しか支払わず、その余の分割代金(傭船料)の支払いを怠ったので、平成10年8月から本船を無償使用していた。
よって、申立人の請求は棄却さるべきである。
第3.証拠
書証として、申立人は甲第1号証乃至第8号証を、被申立入は乙第1号証乃至第12号証を提出した。
理由
- 本件では、当事者間で本船について売買契約と裸傭船契約が同時に締結されていて、両契約の関係が必ずしも明確でない。被申立人が主張するように、取引の実態が買取権付裸傭船契約であるならば、裸傭船契約を主たる契約として傭船料を明確に約定し、それに基づいて傭船料が毎月支払われるとともに、傭船者が本船を買い取る時期と代金額の定めについても明確にすべきところであろう。しかし、本件では傭船料を0円と記入し、両契約締結と同時に売買契約に従って協定書(甲第3号証)を作成し、かつ、協定書中の(2.契約金支払方法)に基づいて申立人が被申立人に手形を交付した事が認められる。一方では、本船の保険契約者が申立人の関係会社であること、本船の引渡しから7カ月以上経過して行われた定期検査が申立人の費用で行われた事実(この点について申立.人が争っているので後に言及する)などがあり、これらから当事者の意思を合理的に解釈すると、本件は、売買契約が主で、裸傭船契約は売買代金完済までの間に生ずる諸費用の負担等について定めたもの、と考えるのが相当である。
- 申立人の請求は、本船の所有権は契約締結と同時に被申立人から申立人に移転しており、本件船舶保険は売買代金残を担保とするためのもので、譲渡担保類似保険であると主張し、保険契約上被申立人が被保険者となっていても、被申立人は保険金及び総連合会からの建造引当金を全額取得する権利を有しないとして、これらの金員を取得した被申立人に対して不当利得に基づく利得の返還を請求すると主張しているものと理解される。そして、申立人が不当利得の根拠としているのは、本船の沈没時の所有権が申立人にあったので、所有権を有しない被申立人が保険金及び建造引当金を取得したことは、法律上の原因なくして取得したものであると主張しているもののようである。申立人は、それを立証するために、船舶売買契約上の所有権移転時期に関する最高裁判所の判決(昭50.1.31判決、甲第6号証)を提出している。これは、所有権移転の時期について特別の定めがなされていない場合に、売買契約締結時に所有権が移転すると判示した事例である。しかるに、本件においては、協定書(甲第3号証)に「所有権移転売買代金が全額決済された時点」と明記されているので、この記載文言が所有権移転時期を特約したものではないことを申立人が立証しなければ、上記判例が本件に妥当しないことば明らかである。申立人は、売買契約の特約欄に「本船売買価格の支払方法については、別紙協定書を作成する。」と記載されていることを根拠に、協定書は代金支払方法を定めたに過ぎず、したがって「所有権移転」とは登記手続のことを言い、第三者への対抗要件は残代金の支払いと同時という意味に解釈すべきであると事張するが、登記手続については、売買契約第3条第3項に「売主は、前項の残代金並びに消費税の受取りと同時に、本船の所有権移転登記をするのに必要な一切の書類…を買主に引き渡す。」と規定されているので、重ねて覚書に登記手続のためという意図で申立人が主張するような内容の規定を設ける必要は全くなかったと言わざるを得ず、覚書の上記文言は、文字どおり所有権移転時期を定めたものにほかならない。したがって、申立人の主張するような申立人への所有権移転を前提として、これに基づく不当利得の主張を認めることはできない。そのほかには申立人は不当利得の根拠に関する主張立証をしておらず、他にこれを認めるべき事実もうかがわれない。
さらに、譲渡担保に関しては申立人において特段の主張も立証もなされていないので、申立人の請求は認められない。
- 保険証券(乙第1号証)の船舶所有者及び被保険者の欄が被申立人になっているのは、裸傭船契約第10条に基づくもので、保険者たるB保険会社が保険証券に従って保険金を被申立人に支払ったのは、正当な行為であると認められる。
- 申立人は保険金精算義務が被申立入にあると主張しているが、その法的根拠もそれを推認させるいかなる事実主張もなされていないので、この主張を認めることができない。
- 次に、申立人は売買契約第4条(船底検査)に基づいて、平成10年9月30日から同年10月5日にかけて行った本船の定期検査費用を請求すると主張しているが、本船の引渡しは、同年2月4日申立外C株式会社で行われたことについて申立人が争っていないので、この定期検査は第4条に基づく船底検査とは別個のものと判断するほかはない。したがって、申立人のこの主張は理由がない。
- 申立人代理人は、従来主張していた不法行為に基づく請求を仲裁においても裁判においても放棄する旨を審尋の席で明言し、請求の根拠は不当利得のみであるとしたので、本件紛議は以上をもって終結する。
- 申立人代理人は、被申立入の行為が刑法上業務上横領に該当すると述べたが、本件仲裁は、民事の紛争についてのものであり、刑法上の主張は何らの意味を有しないし、前述のとおり、申立人は不法行為の主張を放棄しているのであるから、この点については判断するまでもない。
- 仲裁費用
仲裁費用は金1,071,000円(消費税を含む)とし、双方折半して負担するのが適当である。
以上当事者双方の全主張、書証、審尋の結果を総合考慮して、主文のとおり判断する。
2000年7月10日
社団法人日本海運集会所
海事仲裁委員会
仲裁人 野田政則
同 大塚明
同 笹木秀雄
|
※当職は勝利した被申立人の代理人です。


|

|