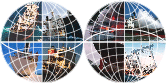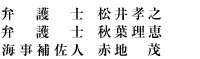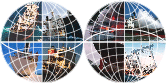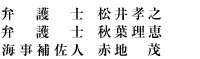|

内航営業権と税務問題
1. 内航海運暫定措置事業の導入と税務問題
- 内航海運については、平成10年5月に、内航海運の活性化を図るため、暫定措置事業を導入するとともに、昭和41年から船腹過剰対策として実施してきたスクラップ・アンド・ビルト方式による船腹調整事業を解消した。
- この暫定措置事業は、保有船舶を解撤等したものに対して一定の交付金を交付するとともに、船舶建造者から納付金を納付させる等を内容とするものである。これは競争制限的と批判が強かった船腹調整事業の解消により、事実上の経済的な価値を有していた引き当て資格が無価値化する経済的影響を考慮したソフトランディング策であるとともに、内航海運の構造改革を推進する観点から、船腹需要の適正化と競争的市場環境の整備を図るための事業である(国土交通省海事局国内貨物課編「内航海運ハンドブック」より)。
- この暫定措置事業によって、内航総連は、保有船舶を解撤するものに交付金を交付する。一方、船舶建造者は、内航総連に納付金を納付(代替建造の場合は、納付金から交付金相当額を相殺する)。内航総連は、この事業に必要な資金を確保するため、独立法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構などの金融機関等か融資を受けて交付金を交付するとともに、船舶建造者が納付する納付金によって、金融機関等からの借入金を返済することになる。
- 本稿では、いわゆる内航の営業権に関して、税務上どのように取り扱うかを検討するものである。内航の営業権の税務をどう取り扱うかは、事業承継、会社の吸収合併などで重要なポイントである。
2. 内航海運暫定措置事業の導入と法人税基本通達等の一部改正について
- 暫定措置事業の導入後、法人税基本通達7-1-5の変更が行われ、「繊維工業における繊機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割り当ての権利を取得するために支出する費用は、営業権に該当するものとする」と変更が加えられ、従来規定されていた「内航海運業のいわゆる建造引当権」が削除されたことは重要である。
- 改正前の上記通達には、「内航海運業のいわゆる建造引当権」が上記営業権のひとつとして列挙されていた。この「内航海運業のいわゆる建造引当権」とは、いわゆる内航の営業権であり、内航海運業界における船腹調整業の実施により船舶の建造が規制される結果、中古船の売買にあたり、中古船の売買とは別に、商慣習として中古船に付着している代替船の建造等の権利として取引の対象とされていたものである(週間税務通信・平成12年3月20日号)。そして、船腹調整事業が平成10年3月に廃止されたために、今後はこのような権利は取引の対象とすることがないと考えられることから、法人税基本通達7-1-5が変更されたといわれている。
- なお、法人が、平成10年3月31日までに実施された船腹調整事業に基づいて取得し、資産計上している建造引当権については、従前どおり営業権として取り扱われることとされている(経過的取扱い(2)、週間税務通信・平成12年3月20日号)。
3. 内航海運暫定措置事業の導入に係る交付金及び納付金の税務上の取扱いについて
- 平成11年5月27日付けの運輸省海上交通局国内貨物課の日本内航海運組合総連合会税務担当宛の「内航海運暫定措置事業の導入に係る交付金及び納付金の税務上の取扱いについて」と称する書面によれば、運輸省と大蔵省及び国税庁との折衝の結果、以下の点が関係官庁間で合意された。
『建造等納付金の税法上の取扱いについては、建造引当権のような権利の取得のための対価ではなく船舶購入のために必要不可欠な費用として、船舶取得価額に算入
納付金免除申講船の納付金免除額の取扱いについては非課税
建造等納付金についての消費税の取扱いについては不課税
解撤等交付金についての消費税の取扱いについては不課税
確認事項
解撤等交付金の取扱いについては、営業権の残存簿価以外は、当該年度の収入に計上すること、を確認した。』
- また、平成16年7月8日の日本内航海運組合総連合会(経理部長 片岡建治氏)が5組合事務局長に宛てた「内航海運暫定措置事業規定の改定に伴う税務上の取扱いについて(事務連絡)」と題する連絡文書によれば、国税局より以下の回答を得たことが明らかになっている。
『総連合会に対する預託金を無利子とすることについて、以下の理由から預託する組合員側において課税の対象とはしない。
(理由)
1. 20%の拠出及び無利子であることが、160億円の新規借入れ実行に当たって政府から示された条件を満たすことになること
2. 無利子であることが総連合会の暫定事業収支の実状からみて経済的合理性が認められること
留保制度に基づき留保された対象トン数の使用承諾(譲渡)を受け、建造等納付金免除船舶として使用する場合の取り扱いについては、次のとおり経理処理する。
- 譲渡した組合員…収益として計上。
- 譲受した組合員…取得時は建設仮勘定として計上し、新規船舶建造時に船価(乗出費用)に計上する。
(理由)
対象トン数の譲受に伴う支出は、新造船取得に伴う費用(乗出費用)として処理することが妥当であること』
- 以上の結果、解撤交付金は損益計算書の対象となり、建造納付金は、貸借対照表の対象となり、本来あるべき会計基準である「収益・費用対応の原則」を逸脱し、内航業者が暫定事業で支払った税金(約400億円)を還元して欲しいなどの批判が生まれる結果となった(内航と海運・平成18年9月号)。
4. 内航海運暫定措置事業の導入後の既存の内航営業権の税務上の評価について
既に述べたように、経過的措置として、平成10年3月31日までに実施された船腹調整事業に基づいて取得し、資産計上している建造引当権については、従前どおり営業権として取り扱われることとされているが、問題は、事業承継や会社の売買などの時価を基準とする税務申告に関わる局面において従来の内航引当資格を如何に評価すべきであるかという点であり、この点は未解決の問題であり、当局ともおおいに見解が分かれる点である。
A説 暫定事業法によれば、保有船舶を解撤するものは内航総連合会から交付金の交付を受けることができる。そこで、従来の内航引当資格の評価は、内航総連合会からの交付金をベースにすべきである。
平成16年度以降は、総連合会の交付金認定の際に20%を預託金として預かることになっており、このような実務から言って、本説は極めて奇説とされている。
B説 従来の内航引当資格に関しては、平成16年以降は引当資格の第三者取引も再開しており、一定の取引相場があるはずであり、これらの市場による相場価格が、事業承継や会社の売買の基準となる時価と税務上は、判断すべきである。
課税は、法律上の財産権または法律上保護された財産上の利益がなければできないものではなく担税力があると認められる事象があれば行いうる。担税力は、経済的な利益があれば十分である。このことは、法律上無効な行為によって得られた利益であっても、所得ありと認められる限りは所得税または法人税の課税対象となることからも明らかである(最高裁昭和46年11月9日)。
C説 暫定措置事業法導入後は、法人税など税務上の観点から言えば、従来の内航引当資格は評価の対象とならない。
5. C説を相当と考える。
筆者は、以下の理由で、C説を相当と考える。
- 暫定措置法以前には、内航船の売買において、内航営業権と船体の価格は別個に金銭評価して、船の値段が定められていた。例えば、海運集会所の内航船舶売買契約書書式においては、本船の売買価格の欄には、内航建造引当権が明記されるようにされている。
しかしながら、暫定措置事業以降は、船舶の売買に関しては、内航引当資格と船体の価格は合わせて(言い換えればブレークダウンすることなく)評価されており、従来の内航引当資格に関しては、(少なくとも)税務裁判で当局が立証しうるほどの一定の取引相場は存在しないのが海運業界の実情である。
- 実現主義からの検討
引当金は将来利用できるかどうか不明確であり、16年超の船令の船舶には交付金も支給されないから、収益が実現していないのだから資産評価するべきではない。未実現の利益(価値の増加利益)は何処の国でも課税の対象から外されている(金子宏「租税法」185頁)。
- 帰属利益の評価または値上益
自己に帰属する利益や評価益は、譲渡して実現される前に資産評価するべきではない。自己所有の財産の利用から得られる経済的利益は、課税の対象から除外される。
- 納付金との関係からみて
イ.建造納付金が安くなるというのは、そのような利用方法があるというだけのことであって、第三者に利用させるのか、解撤するのか、自己使用するのか、暫定事業の終了により、利用不可能となるのかわからないから、資産評価できない。譲渡のとき利益に対して課税すれば十分である。
ロ.自分でいつ作るかわからない。売るかどうかわからない。そのような不確定な引き当て資格を資産評価できない。
ハ.売るかどうかわからない。
ニ.平成10年以降の新造船には交付金がない。平成25年に暫定措置事業は終了することになっている。引き当て資格は、建物賃借人の地位と同じであり、賃借り建物を使用していることについては、資産評価しない。
- 資産評価の原則
未確定なものは評価しない。
- ゴルフ会員権や借地権などとの比較
イ.高額預託会員権を保有していても、ゴルフ場運営会社が破綻していれば時価評価しない。内航総連合会の解撤交付金に関しても、特に平成24年度以降は、今後どのような形になるのかは全く不明である(内航と海運・平成18年9月号)。
ロ.連合会への引当権は、必ず下がるもので上がることはないから、資産性は低い。
ハ.16年超の船令のものは、規約により交付金請求権がない。


|

|